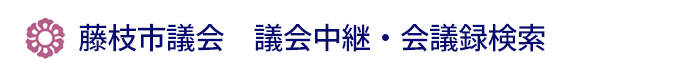質問通告内容
内容
標題1:新年度の施政方針について
5期目の北村市政がスタートして早くも9か月となりますが、公約に掲げられた社会課題への対応、そして将来の成長への礎づくりが着実に進み、コロナ禍を乗り越えて、再び藤枝市が元気に活気づいてきていることを実感しており、また新年度の予算案を拝見しますと、大変きめ細かで積極的な内容であると評価いたします。
一方で、市長の施政方針にもありましたが、現在、国内外ともに社会、経済、そして政治の世界においても激動の中にあり、大きな転換期を迎えております。
こうした状況を見極めながらも、市長が施政方針で力強く述べられたように、次の時代に希望をつなぐ道筋をつけて行く必要があり、来たる令和7年度は、北村市政5期目の大きなステップとなる重要な年になります。
特に、新年度は第6次総合計画の後期計画の策定の年となりますが、こうした転換期の中で、10年、20年先を見据えた取組をどのように確立し、後期計画へとつなげるのか、また、正念場を迎える市政運営の中で、次の時代に向けた新公共経営をどのように進められるのか、令和6年度の締め括りの議会、そして、新年度に向けた施政方針に関連して、以下6つの項目について、藤のまち未来を代表して伺います。
(1)財政と組織改編の取組について
北村市長は施政方針において、令和7年度に向けて3つの取組方針のもとに、当初予算案と組織編成を示されました。まずはこの狙いと具体の取組について以下2点について伺います。
① 今議会に上程された令和7年度の当初予算一般会計の予算規模は、前年度から56億円(9.2%)増の666億8千万円で、過去最大となる極めて積極型の予算となっております。一方で市債残高は北村市長が就任した平成20年度から380億円以上縮減と、着実に財政改革、健全化が進んでいます。
この当初予算の特徴と重点的な施策について市長の所見を伺います。
② 行政組織改編については、私が11月定例月議会で質問し、明確な答弁をいただいたオーガニックシティ推進の専任の組織として「オーガニックのまち推進室」が形となり、たいへん期待するところです。
さて、今回は施政方針の3本柱の1つ「誰もが安心できるまちづくり」として、高齢者や障害者への一元的な対応を図る組織づくりが行われており、市長が5期目の所信表明で述べた「市民目線」が色濃く打ち出されていると考えますが、この組織改編の狙いと具体の取組について伺います。
(2)藤枝市立総合病院の抱える具体的な課題について
市民の命の砦である市立総合病院は、今後さらに安定的な健全経営と医療の高度化を両立していかなければなりません。
こうした中、新型コロナに伴う空床補償が終わり病院経営は大変厳しさを増していると伺っています。これに加えて、施政方針の中でも北村市長は人件費等義務的経費の増大を述べられましたが、これは病院も同じであると考えており、組織編成においても病院支援局内に「経営改革担当理事」を配置することは、経営健全化への強い決意であると期待しております。
病院経営に苦慮しているのは本市だけでなく、県病院協会の調査では8割を超える病院が厳しい経営状況にあるとのことで、毛利病院事業管理者も静岡新聞の記事で病院の機能分担、選択と集中を議論すべきとコメントされています。
そこで、今後の病院経営で抱える具体の課題とその対応について以下3点伺います。
① 医師の働き方改革が進む中でも安定的な医療を提供していくためには、さらに医療従事者の体制を整えていく必要があると考えますが、一方でこれに伴う人件費の増大も課題になります。この現状と今後の見通し、対応策について伺います。
② 病院経営が厳しさを増す中で、これまではたいへんな経営努力により黒字経営を続けられていますが、本年度決算の見通しと今後どのように黒字体制を確保するのか伺います。
③ 人口減少が進む中で、今後は本市だけでなく、志太榛原圏域の各病院も経営が厳しさを増すものと考えます。現在、静岡県においても二次医療圏ごとの医療機能の将来的な必要量を含めた地域医療構想づくりを進めておりますが、本市として今後の志太榛原圏域における医療体制構築を市長はどのように考えているのか伺います。
(3)いじめ・不登校問題と豊かな教育環境の実現に向けて
現在、全国的に学校におけるいじめや暴力行為、またこれらに伴う不登校が深刻さを増しており、長期に亘った新型コロナが子どもを取り巻く環境を大きく変え、拍車をかけたと言われています。
昨年国が公表した実態を見ますと、全国でのいじめの認知件数は73万件を超え過去最多になり、また、小中学校における不登校の児童生徒数も34万人を超え、こちらも過去最多を記録し、未来を担う子どもたちの行動や心が脅かされています。本市においても不登校は増加傾向にあると伺っております。
これに対し、本市では、全ての小中学校に多くの特別支援教育支援員等を手厚く配置するとともに、市内全ての中学校に設置した登校支援教室を、本年度からは一部小学校にも展開するなど、こうした状況への対策・改善に向け大いに期待するところです。
また、教師の長時間労働も課題となる中、その負担となっている部活動指導への対策として部活動の地域移行が進められており、本市においても今年の8月までに全中学校の部活動を地域に移行する方針であります。
そこで、いじめ・不登校問題の状況とその対策、また今後の豊かな教育環境の実現に向けて、以下3点について伺います。
① いじめと不登校の本市における実態と、その対策について伺います。
② 特別支援学級の知的学級・自閉情緒学級、肢体学級の学校別体制の状況と、今後の取組について伺います。
③ 部活動の地域移行におけるその後の進展と課題について伺います。
(4)志太中央幹線と小川島田幹線の事業推進について
本市の交通の根幹を成す志太中央幹線と小川島田幹線は、共に昭和40年代に都市計画決定されていますが、未だかなりの区間が未整備となっています。特にはばたき橋や東名スマートインターチェンジの開通により交通量が激増した県道藤枝大井川線・田沼街道は慢性的な渋滞が発生し、安全・安心をも脅かしています。この抜本的な解決には志太中央幹線の早期開通が不可欠であり、現在、旧国道一号以南の延伸が進められていますが、田沼街道までの接続は見通せていません。
また、この志太中央幹線に高洲地区内で接続する小川島田幹線は、焼津市内では藤枝市境まで整備が進められていますが、藤枝市内では未だ動きが見られません。県道高洲和田線の代替路線として、この小川島田幹線を早期開通させ、志太中央幹線とともに交通分散させることが強く求められます。
そこで、この志太中央幹線、小川島田幹線の事業推進について、以下2点伺います。
① 志太中央幹線の進捗と、今後の整備方針について伺います。
② 県道高洲和田線の代替路線としての小川島田幹線のその後の進捗と、今後の整備方針について伺います。
(5)高洲南地区の交流拠点について
当初予算における令和7年度の重点戦略の中で、私が特に注目したのが「高洲地区コミュニティ施設の整備」であります。
高洲地区におきましては、令和2年8月に地区の総意として、高洲南小学校区への地区交流センター設置の要望書を市長に提出し、私も翌令和3年2月定例月議会の代表質問において、その必要性についてデータを示して、当局の考えを伺いました。これに対して明確な答弁は得られませんでしたが、あれから3年以上が経過し、市全体の人口は減少に転じる中で、当地区はさらに宅地化が進み、地域住民の活動も活発さを増しております。
したがって、その活動・交流、コミュニティの拠点づくりの必要性は益々高まっておりますが、今回の「高洲地区コミュニティ施設の整備」も含め、今後の方向性について、以下2点伺います。
① 地域における住民交流の場づくりは、高齢化が進む中で極めて重要であると考えますが、「高洲地区コミュニティ施設」とは具体にどのようなものを目指すものであるのか、その狙いと具体の内容について伺います。
② 一方で、これは地域が要望している高洲南小学校区への地区交流センター設置の代替えにはなり得ません。地域課題の抜本的解決に向け、この新たな地区交流センターに向けた市長の所見を伺います。
(6)黒石川・小石川沿いの水害対策についての早期の改善策を
高洲・高柳地区は市内でも最も住宅着工率が高い地区であります。人口減少社会の中で、地域人口が増加することは大変喜ばしいことでありますが、宅地化により、かつて地域の多くを占めていた農地は減少し、土や緑が失われると、降った雨の行き場も無くなります。特に、黒石川の河川改修が思うように進んでいないことで、昨今頻発するゲリラ豪雨の度に洗濯川等の小河川からの冠水により、河川沿いの住民は非常に恐怖を感じ、残念ながら長年住み慣れたこの地域から出ていってしまった世帯も数件います。したがって、水害対策、浸水対策は高洲・高柳地区における喫緊の課題であります。当局に置かれましては、部分的に改善策を取っていただいており、また、抜本的解決には焼津市側の改修が必要なことも承知していますが、遅々として進んでいません。大雨の度に恐怖を抱き、その中で、地域総出で土嚢等の対策に当たっている状況を改めて考えていただきたく、これまでも繰り返し質問していますが、以下2点について伺います。
① 今や異常気象ではなく、毎年恒常的に降る大雨によって川沿いの家屋には敷地内浸水が発生し恐怖におののいているこの状況を、当局はどう考えているか伺います。
② 黒石川・小石川沿いの水害対策について、現在の状況と今後の計画について伺います。
5期目の北村市政がスタートして早くも9か月となりますが、公約に掲げられた社会課題への対応、そして将来の成長への礎づくりが着実に進み、コロナ禍を乗り越えて、再び藤枝市が元気に活気づいてきていることを実感しており、また新年度の予算案を拝見しますと、大変きめ細かで積極的な内容であると評価いたします。
一方で、市長の施政方針にもありましたが、現在、国内外ともに社会、経済、そして政治の世界においても激動の中にあり、大きな転換期を迎えております。
こうした状況を見極めながらも、市長が施政方針で力強く述べられたように、次の時代に希望をつなぐ道筋をつけて行く必要があり、来たる令和7年度は、北村市政5期目の大きなステップとなる重要な年になります。
特に、新年度は第6次総合計画の後期計画の策定の年となりますが、こうした転換期の中で、10年、20年先を見据えた取組をどのように確立し、後期計画へとつなげるのか、また、正念場を迎える市政運営の中で、次の時代に向けた新公共経営をどのように進められるのか、令和6年度の締め括りの議会、そして、新年度に向けた施政方針に関連して、以下6つの項目について、藤のまち未来を代表して伺います。
(1)財政と組織改編の取組について
北村市長は施政方針において、令和7年度に向けて3つの取組方針のもとに、当初予算案と組織編成を示されました。まずはこの狙いと具体の取組について以下2点について伺います。
① 今議会に上程された令和7年度の当初予算一般会計の予算規模は、前年度から56億円(9.2%)増の666億8千万円で、過去最大となる極めて積極型の予算となっております。一方で市債残高は北村市長が就任した平成20年度から380億円以上縮減と、着実に財政改革、健全化が進んでいます。
この当初予算の特徴と重点的な施策について市長の所見を伺います。
② 行政組織改編については、私が11月定例月議会で質問し、明確な答弁をいただいたオーガニックシティ推進の専任の組織として「オーガニックのまち推進室」が形となり、たいへん期待するところです。
さて、今回は施政方針の3本柱の1つ「誰もが安心できるまちづくり」として、高齢者や障害者への一元的な対応を図る組織づくりが行われており、市長が5期目の所信表明で述べた「市民目線」が色濃く打ち出されていると考えますが、この組織改編の狙いと具体の取組について伺います。
(2)藤枝市立総合病院の抱える具体的な課題について
市民の命の砦である市立総合病院は、今後さらに安定的な健全経営と医療の高度化を両立していかなければなりません。
こうした中、新型コロナに伴う空床補償が終わり病院経営は大変厳しさを増していると伺っています。これに加えて、施政方針の中でも北村市長は人件費等義務的経費の増大を述べられましたが、これは病院も同じであると考えており、組織編成においても病院支援局内に「経営改革担当理事」を配置することは、経営健全化への強い決意であると期待しております。
病院経営に苦慮しているのは本市だけでなく、県病院協会の調査では8割を超える病院が厳しい経営状況にあるとのことで、毛利病院事業管理者も静岡新聞の記事で病院の機能分担、選択と集中を議論すべきとコメントされています。
そこで、今後の病院経営で抱える具体の課題とその対応について以下3点伺います。
① 医師の働き方改革が進む中でも安定的な医療を提供していくためには、さらに医療従事者の体制を整えていく必要があると考えますが、一方でこれに伴う人件費の増大も課題になります。この現状と今後の見通し、対応策について伺います。
② 病院経営が厳しさを増す中で、これまではたいへんな経営努力により黒字経営を続けられていますが、本年度決算の見通しと今後どのように黒字体制を確保するのか伺います。
③ 人口減少が進む中で、今後は本市だけでなく、志太榛原圏域の各病院も経営が厳しさを増すものと考えます。現在、静岡県においても二次医療圏ごとの医療機能の将来的な必要量を含めた地域医療構想づくりを進めておりますが、本市として今後の志太榛原圏域における医療体制構築を市長はどのように考えているのか伺います。
(3)いじめ・不登校問題と豊かな教育環境の実現に向けて
現在、全国的に学校におけるいじめや暴力行為、またこれらに伴う不登校が深刻さを増しており、長期に亘った新型コロナが子どもを取り巻く環境を大きく変え、拍車をかけたと言われています。
昨年国が公表した実態を見ますと、全国でのいじめの認知件数は73万件を超え過去最多になり、また、小中学校における不登校の児童生徒数も34万人を超え、こちらも過去最多を記録し、未来を担う子どもたちの行動や心が脅かされています。本市においても不登校は増加傾向にあると伺っております。
これに対し、本市では、全ての小中学校に多くの特別支援教育支援員等を手厚く配置するとともに、市内全ての中学校に設置した登校支援教室を、本年度からは一部小学校にも展開するなど、こうした状況への対策・改善に向け大いに期待するところです。
また、教師の長時間労働も課題となる中、その負担となっている部活動指導への対策として部活動の地域移行が進められており、本市においても今年の8月までに全中学校の部活動を地域に移行する方針であります。
そこで、いじめ・不登校問題の状況とその対策、また今後の豊かな教育環境の実現に向けて、以下3点について伺います。
① いじめと不登校の本市における実態と、その対策について伺います。
② 特別支援学級の知的学級・自閉情緒学級、肢体学級の学校別体制の状況と、今後の取組について伺います。
③ 部活動の地域移行におけるその後の進展と課題について伺います。
(4)志太中央幹線と小川島田幹線の事業推進について
本市の交通の根幹を成す志太中央幹線と小川島田幹線は、共に昭和40年代に都市計画決定されていますが、未だかなりの区間が未整備となっています。特にはばたき橋や東名スマートインターチェンジの開通により交通量が激増した県道藤枝大井川線・田沼街道は慢性的な渋滞が発生し、安全・安心をも脅かしています。この抜本的な解決には志太中央幹線の早期開通が不可欠であり、現在、旧国道一号以南の延伸が進められていますが、田沼街道までの接続は見通せていません。
また、この志太中央幹線に高洲地区内で接続する小川島田幹線は、焼津市内では藤枝市境まで整備が進められていますが、藤枝市内では未だ動きが見られません。県道高洲和田線の代替路線として、この小川島田幹線を早期開通させ、志太中央幹線とともに交通分散させることが強く求められます。
そこで、この志太中央幹線、小川島田幹線の事業推進について、以下2点伺います。
① 志太中央幹線の進捗と、今後の整備方針について伺います。
② 県道高洲和田線の代替路線としての小川島田幹線のその後の進捗と、今後の整備方針について伺います。
(5)高洲南地区の交流拠点について
当初予算における令和7年度の重点戦略の中で、私が特に注目したのが「高洲地区コミュニティ施設の整備」であります。
高洲地区におきましては、令和2年8月に地区の総意として、高洲南小学校区への地区交流センター設置の要望書を市長に提出し、私も翌令和3年2月定例月議会の代表質問において、その必要性についてデータを示して、当局の考えを伺いました。これに対して明確な答弁は得られませんでしたが、あれから3年以上が経過し、市全体の人口は減少に転じる中で、当地区はさらに宅地化が進み、地域住民の活動も活発さを増しております。
したがって、その活動・交流、コミュニティの拠点づくりの必要性は益々高まっておりますが、今回の「高洲地区コミュニティ施設の整備」も含め、今後の方向性について、以下2点伺います。
① 地域における住民交流の場づくりは、高齢化が進む中で極めて重要であると考えますが、「高洲地区コミュニティ施設」とは具体にどのようなものを目指すものであるのか、その狙いと具体の内容について伺います。
② 一方で、これは地域が要望している高洲南小学校区への地区交流センター設置の代替えにはなり得ません。地域課題の抜本的解決に向け、この新たな地区交流センターに向けた市長の所見を伺います。
(6)黒石川・小石川沿いの水害対策についての早期の改善策を
高洲・高柳地区は市内でも最も住宅着工率が高い地区であります。人口減少社会の中で、地域人口が増加することは大変喜ばしいことでありますが、宅地化により、かつて地域の多くを占めていた農地は減少し、土や緑が失われると、降った雨の行き場も無くなります。特に、黒石川の河川改修が思うように進んでいないことで、昨今頻発するゲリラ豪雨の度に洗濯川等の小河川からの冠水により、河川沿いの住民は非常に恐怖を感じ、残念ながら長年住み慣れたこの地域から出ていってしまった世帯も数件います。したがって、水害対策、浸水対策は高洲・高柳地区における喫緊の課題であります。当局に置かれましては、部分的に改善策を取っていただいており、また、抜本的解決には焼津市側の改修が必要なことも承知していますが、遅々として進んでいません。大雨の度に恐怖を抱き、その中で、地域総出で土嚢等の対策に当たっている状況を改めて考えていただきたく、これまでも繰り返し質問していますが、以下2点について伺います。
① 今や異常気象ではなく、毎年恒常的に降る大雨によって川沿いの家屋には敷地内浸水が発生し恐怖におののいているこの状況を、当局はどう考えているか伺います。
② 黒石川・小石川沿いの水害対策について、現在の状況と今後の計画について伺います。