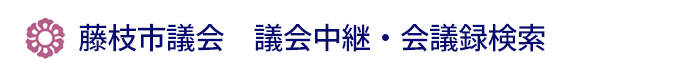質問通告内容
内容
標題1:障がい者の福祉施設通所の交通費補助及び生活困窮者の居場所づくりについて
施政方針で「誰もが安心できるまちづくり」と謳い、「障害のある方が福祉施設に通うための交通費の支援や、生活に困窮する方の地域での居場所づくりに新規に取り組む」と具体的な項目に触れている。
この2項目は、昨年市民の声を受け議会で取り上げたものであり、実現の運びとなった事を嬉しく思う。
同時に、中身が利用者の立場に寄り添ったものであるかどうか、下記質問する。
(1)障がい者の通所支援について。現在でも市内の静鉄バスが半額の助成としているが、運賃そのものが高く残りの半額の負担が大変である。また、JRは半額の助成があるものの、片道100km以上でないと対象にならず、静岡に通う場合は対象外である。この現状に則した制度となっているか。
(2)居場所づくりについて。現在も居場所はあるが、週一の開所であったり、障がいの有無が条件であったり、義務教育終了後引きこもりにある人たちが、気軽に立ち寄れる場所が近隣では掛川にしかない実態であった。この現状に則した制度となっているか。
(3)施政方針には「高齢化が進展する中で、孤立や複合的な課題を抱えるケースが増している」としており、その対策として有用な補聴器購入費助成制度は、今年度予算において300万円から400万円と増額がされた。
内容は補聴器購入後、5年後に新たに購入する人が多いというアンケート結果による増額だが、決算委員会が提言したのは5万円の限度額に対する増、対象条件の住民税非課税世帯からの拡大であった。提言したからといって全てが実現するとは考えないが、1,000以上もの事業から絞りに絞って最終的に11の事業を選び、議論を重ねて、全会一致として議会がまとめ上げてきたものである。総括質疑でも指摘したが、令和7年度予算での検討はどうであったか。
標題2:予定より30億円以上も増額予算となった新学校給食センター整備事業費について
令和7年度予算で、新学校給食センター整備事業費として、合計78億7千万円(建設工事費等60億2千万円、厨房機器等購入費18億5千万円)を限度額とする債務負担行為(令和8年度から令和9年度まで)が設定されている。
令和4年5月に、本市が策定した新学校給食センター基本計画及び基本構想では、総事業費を約50億円と見込んでいる。
また、令和5年2月議会の当初予算案に対する私の議案質疑においても、市は総事業費47億6千万円余と答えている。
昨今の物価高、資材不足などで、総じて工事費が上昇する傾向は否めないが、30億円もの増額の予算設定となった原因は、どこにあるのか。
また、既に用地取得のための予算(約3億2千万円)が昨年11月議会で可決されている上、令和5年以降これまで6億5千万円の事業費となっている。
今後必要となる現在の北部西部両センターの解体工事費は50億円の見込み額に含まれており、想定額との“乖離”は今以上に膨らむことになる。
想定額がどのように算定されているのか、それに対する予算がどのように組み立てられているのか、など、市民の理解が得られる説明を。
標題3:「地域医療連携推進法人」で何を目指すのか
4月から市立病院と聖稜リハビリテーション病院の2者を参加法人とする地域医療連携推進法人が創設される。
地域医療構想実現のため、国の制度に則った法人設立であるが、急性期から回復期への転院を円滑化する事などが挙げられている。
厚生労働省は、法制度のメリットとして、病床過剰地域においても参加法人間での病床融通が可能となる点や、法人から参加法人への資金貸付、患者紹介、逆紹介の円滑化などを示している。
(1)現在、市立病院から聖稜リハへの逆紹介が順調に行われていない実態があるのか。
(2)病床過剰地域からの脱却がほぼ不可能な現状であり、かつ、聖稜リハの増築が出来ないのに、あえて法人化を進める理由はどこにあるか。
(3)将来は、2法人以上の連携が許されており、現在の市立病院における空きベッド(564床のうち、実稼働していない約100床)を他へ融通する事が制度上可能となっており、市立病院の病床削減の口実になりかねない。今後その方針を持たないと明言できるか。
(4)小泉改革以来、病診連携が進められてきたが、市民の願いは転院することなく完治するまで市立病院で診療を受ける事である。空きベットを融通するような計画ではなく、かつてあった療養型病床を市立病院に復活させる方向性を示していくべきではないか。
標題4:先進坑掘削を進めるJRに対し約束した調査の実施を
知事が交代した事で、リニアが危うい状況に急加速している。
北村市長も参加している大井川利水関係協議会(利水協)のこれまでの役割が改めて問われる状況になっており、約束を反故にしたJRに対して水を守る立場を堅持する市長の立場を鮮明にしていただくべく、現状から下記質問をする。
(1)もともと利水協が合意した「田代ダム案」(県境に向け10か月の工事期間中は山梨県側に湧水するので、早川に放出している田代ダムの水を大井川に放水する事で水量を維持する)は、そもそもの湧水量500万㌧は「不確実性を伴う」ものであり、大井川の年間流量19億㌧と比べ0.3%に過ぎない「誤差の範囲」(染谷市長)発言は見当違いな比較であるので、高速長尺先進ボーリングによる調査を了承したという前提で間違いないか。
(2)利水協は、上記の調査を田代ダムの設備改修の期間内(令和8年11月)で実施する事で了承、県知事交代前後の5月13日に県専門部会がJRに対し、断層2における湧水量の想定と、断層2の湧水が山梨静岡どちらの由来になるかの成分分析を実施する事を「逆提案」する形でボーリング再開を合意、6月の静岡山梨両知事とJRの三者合意につながった。経緯は、この通りでよいか。
(3)ところが県境100m手前でボーリング調査が出来ていなかった事が2か月後の12月の専門部会で判明。その一方で、県や県民になんら知らせることなく11月20日にJRは県境を10m超えてボーリング調査を行い、これを成果のごとく言いふらし、事もあろうかボーリングの(12㎝)60倍もの直径(7m)もの先進坑工事を開始している。これは利水協合意に対する明白な違反であり、約束通りの調査をするよう求める事が必要ではないか。
(4)1月29日、北村市長始め流域8首長が、国に対して、①JRに対して先進坑掘削に対する指導②水資源に影響が出た時の補償の申し入れを行っているが、一旦水が枯れた場合の補償を一企業であるJRがどうやって未来永劫行えるのか。求めるのは、そこではないのではないか。
(5)翌日(1月30日)知事とJRが二度目の会談を持った際、JRは名古屋開業後に1時間1本の静岡停車のひかりを2本に増発すると提示した。現在でも静岡駅乗車率は5割程度であり、何年先か見通しもつかない名古屋開通後に本数を増やしてどれほどの経済効果があるのか。そもそも、水と環境の問題とは別次元の事ではないか。
施政方針で「誰もが安心できるまちづくり」と謳い、「障害のある方が福祉施設に通うための交通費の支援や、生活に困窮する方の地域での居場所づくりに新規に取り組む」と具体的な項目に触れている。
この2項目は、昨年市民の声を受け議会で取り上げたものであり、実現の運びとなった事を嬉しく思う。
同時に、中身が利用者の立場に寄り添ったものであるかどうか、下記質問する。
(1)障がい者の通所支援について。現在でも市内の静鉄バスが半額の助成としているが、運賃そのものが高く残りの半額の負担が大変である。また、JRは半額の助成があるものの、片道100km以上でないと対象にならず、静岡に通う場合は対象外である。この現状に則した制度となっているか。
(2)居場所づくりについて。現在も居場所はあるが、週一の開所であったり、障がいの有無が条件であったり、義務教育終了後引きこもりにある人たちが、気軽に立ち寄れる場所が近隣では掛川にしかない実態であった。この現状に則した制度となっているか。
(3)施政方針には「高齢化が進展する中で、孤立や複合的な課題を抱えるケースが増している」としており、その対策として有用な補聴器購入費助成制度は、今年度予算において300万円から400万円と増額がされた。
内容は補聴器購入後、5年後に新たに購入する人が多いというアンケート結果による増額だが、決算委員会が提言したのは5万円の限度額に対する増、対象条件の住民税非課税世帯からの拡大であった。提言したからといって全てが実現するとは考えないが、1,000以上もの事業から絞りに絞って最終的に11の事業を選び、議論を重ねて、全会一致として議会がまとめ上げてきたものである。総括質疑でも指摘したが、令和7年度予算での検討はどうであったか。
標題2:予定より30億円以上も増額予算となった新学校給食センター整備事業費について
令和7年度予算で、新学校給食センター整備事業費として、合計78億7千万円(建設工事費等60億2千万円、厨房機器等購入費18億5千万円)を限度額とする債務負担行為(令和8年度から令和9年度まで)が設定されている。
令和4年5月に、本市が策定した新学校給食センター基本計画及び基本構想では、総事業費を約50億円と見込んでいる。
また、令和5年2月議会の当初予算案に対する私の議案質疑においても、市は総事業費47億6千万円余と答えている。
昨今の物価高、資材不足などで、総じて工事費が上昇する傾向は否めないが、30億円もの増額の予算設定となった原因は、どこにあるのか。
また、既に用地取得のための予算(約3億2千万円)が昨年11月議会で可決されている上、令和5年以降これまで6億5千万円の事業費となっている。
今後必要となる現在の北部西部両センターの解体工事費は50億円の見込み額に含まれており、想定額との“乖離”は今以上に膨らむことになる。
想定額がどのように算定されているのか、それに対する予算がどのように組み立てられているのか、など、市民の理解が得られる説明を。
標題3:「地域医療連携推進法人」で何を目指すのか
4月から市立病院と聖稜リハビリテーション病院の2者を参加法人とする地域医療連携推進法人が創設される。
地域医療構想実現のため、国の制度に則った法人設立であるが、急性期から回復期への転院を円滑化する事などが挙げられている。
厚生労働省は、法制度のメリットとして、病床過剰地域においても参加法人間での病床融通が可能となる点や、法人から参加法人への資金貸付、患者紹介、逆紹介の円滑化などを示している。
(1)現在、市立病院から聖稜リハへの逆紹介が順調に行われていない実態があるのか。
(2)病床過剰地域からの脱却がほぼ不可能な現状であり、かつ、聖稜リハの増築が出来ないのに、あえて法人化を進める理由はどこにあるか。
(3)将来は、2法人以上の連携が許されており、現在の市立病院における空きベッド(564床のうち、実稼働していない約100床)を他へ融通する事が制度上可能となっており、市立病院の病床削減の口実になりかねない。今後その方針を持たないと明言できるか。
(4)小泉改革以来、病診連携が進められてきたが、市民の願いは転院することなく完治するまで市立病院で診療を受ける事である。空きベットを融通するような計画ではなく、かつてあった療養型病床を市立病院に復活させる方向性を示していくべきではないか。
標題4:先進坑掘削を進めるJRに対し約束した調査の実施を
知事が交代した事で、リニアが危うい状況に急加速している。
北村市長も参加している大井川利水関係協議会(利水協)のこれまでの役割が改めて問われる状況になっており、約束を反故にしたJRに対して水を守る立場を堅持する市長の立場を鮮明にしていただくべく、現状から下記質問をする。
(1)もともと利水協が合意した「田代ダム案」(県境に向け10か月の工事期間中は山梨県側に湧水するので、早川に放出している田代ダムの水を大井川に放水する事で水量を維持する)は、そもそもの湧水量500万㌧は「不確実性を伴う」ものであり、大井川の年間流量19億㌧と比べ0.3%に過ぎない「誤差の範囲」(染谷市長)発言は見当違いな比較であるので、高速長尺先進ボーリングによる調査を了承したという前提で間違いないか。
(2)利水協は、上記の調査を田代ダムの設備改修の期間内(令和8年11月)で実施する事で了承、県知事交代前後の5月13日に県専門部会がJRに対し、断層2における湧水量の想定と、断層2の湧水が山梨静岡どちらの由来になるかの成分分析を実施する事を「逆提案」する形でボーリング再開を合意、6月の静岡山梨両知事とJRの三者合意につながった。経緯は、この通りでよいか。
(3)ところが県境100m手前でボーリング調査が出来ていなかった事が2か月後の12月の専門部会で判明。その一方で、県や県民になんら知らせることなく11月20日にJRは県境を10m超えてボーリング調査を行い、これを成果のごとく言いふらし、事もあろうかボーリングの(12㎝)60倍もの直径(7m)もの先進坑工事を開始している。これは利水協合意に対する明白な違反であり、約束通りの調査をするよう求める事が必要ではないか。
(4)1月29日、北村市長始め流域8首長が、国に対して、①JRに対して先進坑掘削に対する指導②水資源に影響が出た時の補償の申し入れを行っているが、一旦水が枯れた場合の補償を一企業であるJRがどうやって未来永劫行えるのか。求めるのは、そこではないのではないか。
(5)翌日(1月30日)知事とJRが二度目の会談を持った際、JRは名古屋開業後に1時間1本の静岡停車のひかりを2本に増発すると提示した。現在でも静岡駅乗車率は5割程度であり、何年先か見通しもつかない名古屋開通後に本数を増やしてどれほどの経済効果があるのか。そもそも、水と環境の問題とは別次元の事ではないか。