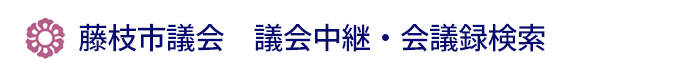質問通告内容
内容
標題1:手話言語条例について
「障害者差別解消法」など障がい者福祉への取り組みは徐々に進んできたところですが、聴覚障がいに関する地方自治体の動きとして「手話言語条例」を制定する自治体が広がってきている点が挙げられます。
全国で最初に制定したのは鳥取県で平成25(2013)年10月とされていますが「一般財団法人 全日本ろうあ連盟」の調査によると、令和2(2020)年8月の段階で制定していた自治体は360でしたが、本年1月末現在では556自治体となっています。
また本年は聴覚障がい者の国際スポーツ大会「デフリンピック」が東京・福島・静岡の1都2県の施設を会場に開催されることから、国会では手話のさらなる普及を目的に「手話に関する施策の推進に関する法律案」(略称:手話施策推進法案)の成立を目指す動きもあります。
さて、全日本ろうあ連盟のホームページでは、全国の地方自治体のうち条例を制定した自治体を掲載しているのですが、藤枝市は掲載されていません。
しかし、藤枝市では1月に実施されたリバティ駅伝でも手話通訳者が活躍されていた様に、既に取り組みをされているところです。
そこで、先に述べた条例を制定してきている自治体の広がりや今後の動きなどから、本市においても「手話言語条例」の制定を求めたいのですが、お考えを伺います。
標題2:発達支援について
(1)5歳児健診への対応について
こども家庭庁では令和7年度から、発達障がいの可能性を見極めるのに有効とされている「5歳児健診」の普及に取り組んでいくことが報道されていました。
令和4年度時点で全国の地方自治体における「5歳児健診」の実施率は約14%とも紹介されていましたが、令和10(2028)年度までに100%を目標としているとのことでした。
藤枝市では現在「5歳児健診」を実施しておりませんので状況とお考えについて伺います。
(2)居宅訪問型児童発達支援について
国では福祉サービスのメニューを幾つか提示していますが、その中の「居宅訪問型児童発達支援」について伺います。
以前は「重度障がい児」が対象の様に理解されていた福祉サービスですが、「精神障がいや行動障がいによって外出や集団での生活が著しく困難である障がい児(就学児を含む)もこの対象になり得る。」との見解が昨年国から出されました。しかし、各自治体における現場ではまだまだ徹底されていない様にも感じられます。
この支援事業を実施している事業所が地域に存在しているのかという問題はありますが、保護者にとっても有り難い制度であり柔軟に対応していただきたいと思うところです。対象者がいた場合の対応についての見解を伺います。
(3)発達障がいの啓発について
発達障がいは幼少期にその特性を見つけることが多い様に思われますが、成人になってからその特性に気付くことがあります。
平成28(2016)年に行われた調査(生活のしづらさなどに関する調査 -厚生労働省 社会・援護局障害保健福祉部)では、0歳〜19歳で発達障がいと診断された方は全国で約22万5千人だったのに対し、同じ年に診断された20歳以上の方は約24万3千人という結果でした。
何よりも早期発見が大切であり、早期に自身の特性を知ることは、その後の治療や日常生活にも影響をしてきます。政府広報オンラインでも「大人になって気づく発達障害」というサイトを設けていますが、乳幼児期から成人に至るまで、啓発や学びのサイトは複数存在しています。
さて、毎年4月2日は「世界自閉症啓発デー」であり、4月2日〜8日は「発達障害啓発週間」になっておりますので啓発をしていただくとともに、市ホームページの関連する課のところに発達障がいに関するサイトへのリンクの設置を求めたいのですがお考えを伺います。
標題3:防犯対策機器への補助について
昨今、侵入強盗や特殊詐欺などのニュースを耳にすることが多くなりました。インターホンが鳴ったので玄関に出てみると誰もいなかったり、犯罪者が業者を装ってインターホンを鳴らしたりしてきます。
家に人を入れる前にはインターホンで対応する場合が多いですが、防犯対策としてはチャイムのみのインターホンに較べ「録画機能付きドアホン」は犯罪抑止効果があり、実際にドアホンの録画映像が決め手となって犯人が特定でき、逮捕につながった事例もある様です。
令和7年度の取組方針ではその1つに「誰もが安心できるまちづくり」 を掲げており、既に防犯灯への設置補助や特殊詐欺電話等防止機器への購入費補助などは実施しているところですが、「録画機能付きドアホン」など住居における防犯対策用品の補助もご検討をいただきたいと思います。
藤枝市は犯罪の少ないまちではありますが、さらなる市民への啓発と防犯対策を推進していく上で取り組んでいくことが出来ないか伺います。
標題4:インクルーシブ遊具について
令和7年度の事業に、年齢・性別・障がいの有無に関わらず誰もが楽しく利用できる公園を整備する。とのことで「都市公園インクルーシブ推進事業」を新規事業として加えていただきました。
昨年の9月定例月議会での一般質問で、市長にユニバーサルデザインに対するご所見を伺い、その後に遊具を設置する場所については「市のバリアフリー化重点地区で、賑わいの拠点と位置付ける駅南公園に先行して設置する検討をしている」との答弁でした。
今まで市内の公園に設置されている遊具では遊ぶことのできない特性のあるお子さんやその保護者にとって、この遊具の設置は朗報だと思います。
まだ設置もされていないので少々気が早いとは思いますが、「先行して」と答弁をしていただいておりますので今後についてのお考えを伺います。
標題5:サッカー交流と関係人口について
サッカーのまち100年の記念すべき年を過ぎ、これから新たな歴史を刻んでいくことになります。
そのスタートにあたって藤枝順心高校女子サッカー部の全日本高校女子サッカー選手権大会3連覇は、市長も優勝報告会で述べられていましたが、藤枝市の名前を全国にとどろかせた次の100年に向けて幸先の良いものでした。
新年度では新規事業も計画されているところですが、「サッカーを核としたまちづくりの推進について」というような項目で視察に訪れる議会の委員会や会派もあり、1月に議会改革に関する視察で訪れてくれた滋賀県彦根市議会の議会運営委員長は地元にJFLに所属するチームがあることから、改めて蹴球都市としての取り組みについて視察に訪れたい。とも言われていました。
1月25日・26日の2日間、藤枝総合運動公園サッカー場を中心として「もうひとつの高校選手権大会」(全国知的障害特別支援学校高等部サッカー選手権大会)の第10回大会が開催されました。
この大会には以前、市長にも会場に足を運んでいただきましたが、今回初日には日本障がい者サッカー連盟の北澤豪会長も来場されました。
私も初日に会場に行きましたが、アイントラハト・フランクフルトアカデミージャパンの成川代表と話しをすることも出来、既にアカデミーに関係している方がドイツから藤枝市に何回も来られていることを知りました。また、成川代表からお話しがあったことによりサッカー交流として台湾新竹縣の小学生と保護者が藤枝市に来られました。
今後、シティ・トレセン構想も進められていきますが、現在の「サッカーのまち藤枝ドリームプラン」も令和7年度が最終年度であり、「Next100 スポーツツーリズムプロジェクト」の成果報告会が行われたところでもありますので、サッカーを通じての交流や関係人口の構築について、次のステージに向けてのご所見を伺います。
標題6:ローカルSDGsの評価について
平成27(2015)年の国連総会で採択された「持続可能な開発目標」(SDGs)も、達成期限とされている2030年まで5年を切りました。
国際研究組織である「持続可能な開発ソリューション・ネットワーク」(SDSN)は、毎年6月に各国の進捗状況を評価し発表をしていますが、昨年の発表で日本は167カ国中18位と過去最も高位置となっていました。
藤枝市では、ローカルSDGsを設けていますが、藤枝市第6次総合計画の前期5カ年の最終年度ということでもあり、藤枝市版ローカルSDGsについて進捗状況の評価をすべきではないかと思いますのでお考えを伺います。
「障害者差別解消法」など障がい者福祉への取り組みは徐々に進んできたところですが、聴覚障がいに関する地方自治体の動きとして「手話言語条例」を制定する自治体が広がってきている点が挙げられます。
全国で最初に制定したのは鳥取県で平成25(2013)年10月とされていますが「一般財団法人 全日本ろうあ連盟」の調査によると、令和2(2020)年8月の段階で制定していた自治体は360でしたが、本年1月末現在では556自治体となっています。
また本年は聴覚障がい者の国際スポーツ大会「デフリンピック」が東京・福島・静岡の1都2県の施設を会場に開催されることから、国会では手話のさらなる普及を目的に「手話に関する施策の推進に関する法律案」(略称:手話施策推進法案)の成立を目指す動きもあります。
さて、全日本ろうあ連盟のホームページでは、全国の地方自治体のうち条例を制定した自治体を掲載しているのですが、藤枝市は掲載されていません。
しかし、藤枝市では1月に実施されたリバティ駅伝でも手話通訳者が活躍されていた様に、既に取り組みをされているところです。
そこで、先に述べた条例を制定してきている自治体の広がりや今後の動きなどから、本市においても「手話言語条例」の制定を求めたいのですが、お考えを伺います。
標題2:発達支援について
(1)5歳児健診への対応について
こども家庭庁では令和7年度から、発達障がいの可能性を見極めるのに有効とされている「5歳児健診」の普及に取り組んでいくことが報道されていました。
令和4年度時点で全国の地方自治体における「5歳児健診」の実施率は約14%とも紹介されていましたが、令和10(2028)年度までに100%を目標としているとのことでした。
藤枝市では現在「5歳児健診」を実施しておりませんので状況とお考えについて伺います。
(2)居宅訪問型児童発達支援について
国では福祉サービスのメニューを幾つか提示していますが、その中の「居宅訪問型児童発達支援」について伺います。
以前は「重度障がい児」が対象の様に理解されていた福祉サービスですが、「精神障がいや行動障がいによって外出や集団での生活が著しく困難である障がい児(就学児を含む)もこの対象になり得る。」との見解が昨年国から出されました。しかし、各自治体における現場ではまだまだ徹底されていない様にも感じられます。
この支援事業を実施している事業所が地域に存在しているのかという問題はありますが、保護者にとっても有り難い制度であり柔軟に対応していただきたいと思うところです。対象者がいた場合の対応についての見解を伺います。
(3)発達障がいの啓発について
発達障がいは幼少期にその特性を見つけることが多い様に思われますが、成人になってからその特性に気付くことがあります。
平成28(2016)年に行われた調査(生活のしづらさなどに関する調査 -厚生労働省 社会・援護局障害保健福祉部)では、0歳〜19歳で発達障がいと診断された方は全国で約22万5千人だったのに対し、同じ年に診断された20歳以上の方は約24万3千人という結果でした。
何よりも早期発見が大切であり、早期に自身の特性を知ることは、その後の治療や日常生活にも影響をしてきます。政府広報オンラインでも「大人になって気づく発達障害」というサイトを設けていますが、乳幼児期から成人に至るまで、啓発や学びのサイトは複数存在しています。
さて、毎年4月2日は「世界自閉症啓発デー」であり、4月2日〜8日は「発達障害啓発週間」になっておりますので啓発をしていただくとともに、市ホームページの関連する課のところに発達障がいに関するサイトへのリンクの設置を求めたいのですがお考えを伺います。
標題3:防犯対策機器への補助について
昨今、侵入強盗や特殊詐欺などのニュースを耳にすることが多くなりました。インターホンが鳴ったので玄関に出てみると誰もいなかったり、犯罪者が業者を装ってインターホンを鳴らしたりしてきます。
家に人を入れる前にはインターホンで対応する場合が多いですが、防犯対策としてはチャイムのみのインターホンに較べ「録画機能付きドアホン」は犯罪抑止効果があり、実際にドアホンの録画映像が決め手となって犯人が特定でき、逮捕につながった事例もある様です。
令和7年度の取組方針ではその1つに「誰もが安心できるまちづくり」 を掲げており、既に防犯灯への設置補助や特殊詐欺電話等防止機器への購入費補助などは実施しているところですが、「録画機能付きドアホン」など住居における防犯対策用品の補助もご検討をいただきたいと思います。
藤枝市は犯罪の少ないまちではありますが、さらなる市民への啓発と防犯対策を推進していく上で取り組んでいくことが出来ないか伺います。
標題4:インクルーシブ遊具について
令和7年度の事業に、年齢・性別・障がいの有無に関わらず誰もが楽しく利用できる公園を整備する。とのことで「都市公園インクルーシブ推進事業」を新規事業として加えていただきました。
昨年の9月定例月議会での一般質問で、市長にユニバーサルデザインに対するご所見を伺い、その後に遊具を設置する場所については「市のバリアフリー化重点地区で、賑わいの拠点と位置付ける駅南公園に先行して設置する検討をしている」との答弁でした。
今まで市内の公園に設置されている遊具では遊ぶことのできない特性のあるお子さんやその保護者にとって、この遊具の設置は朗報だと思います。
まだ設置もされていないので少々気が早いとは思いますが、「先行して」と答弁をしていただいておりますので今後についてのお考えを伺います。
標題5:サッカー交流と関係人口について
サッカーのまち100年の記念すべき年を過ぎ、これから新たな歴史を刻んでいくことになります。
そのスタートにあたって藤枝順心高校女子サッカー部の全日本高校女子サッカー選手権大会3連覇は、市長も優勝報告会で述べられていましたが、藤枝市の名前を全国にとどろかせた次の100年に向けて幸先の良いものでした。
新年度では新規事業も計画されているところですが、「サッカーを核としたまちづくりの推進について」というような項目で視察に訪れる議会の委員会や会派もあり、1月に議会改革に関する視察で訪れてくれた滋賀県彦根市議会の議会運営委員長は地元にJFLに所属するチームがあることから、改めて蹴球都市としての取り組みについて視察に訪れたい。とも言われていました。
1月25日・26日の2日間、藤枝総合運動公園サッカー場を中心として「もうひとつの高校選手権大会」(全国知的障害特別支援学校高等部サッカー選手権大会)の第10回大会が開催されました。
この大会には以前、市長にも会場に足を運んでいただきましたが、今回初日には日本障がい者サッカー連盟の北澤豪会長も来場されました。
私も初日に会場に行きましたが、アイントラハト・フランクフルトアカデミージャパンの成川代表と話しをすることも出来、既にアカデミーに関係している方がドイツから藤枝市に何回も来られていることを知りました。また、成川代表からお話しがあったことによりサッカー交流として台湾新竹縣の小学生と保護者が藤枝市に来られました。
今後、シティ・トレセン構想も進められていきますが、現在の「サッカーのまち藤枝ドリームプラン」も令和7年度が最終年度であり、「Next100 スポーツツーリズムプロジェクト」の成果報告会が行われたところでもありますので、サッカーを通じての交流や関係人口の構築について、次のステージに向けてのご所見を伺います。
標題6:ローカルSDGsの評価について
平成27(2015)年の国連総会で採択された「持続可能な開発目標」(SDGs)も、達成期限とされている2030年まで5年を切りました。
国際研究組織である「持続可能な開発ソリューション・ネットワーク」(SDSN)は、毎年6月に各国の進捗状況を評価し発表をしていますが、昨年の発表で日本は167カ国中18位と過去最も高位置となっていました。
藤枝市では、ローカルSDGsを設けていますが、藤枝市第6次総合計画の前期5カ年の最終年度ということでもあり、藤枝市版ローカルSDGsについて進捗状況の評価をすべきではないかと思いますのでお考えを伺います。