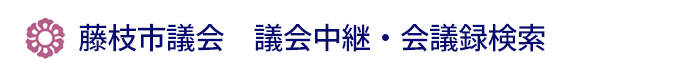質問通告内容
内容
標題1:藤枝シティ・トレセン構想について
藤枝シティ・トレセン構想は、各種スポーツ施設や地域資源を生かした本市独自のスポーツ交流戦略のことであり、スポーツを核に市内全域をフィールドに、国内外からサッカーを始め多様なスポーツ活動や交流を呼び込んで、幅広い世代が集い交流できる滞在型のまちづくりを目指すというもの。
本市がサッカーのまちとして特色あるまちづくりに取り組み、スポーツや交流が活発になることは良いことと考える。しかし、スポーツは健康や元気に大いに影響するものではあるが、生活の中での優先度は低く、大会やイベント参加は多くの高齢者や、仕事子育てに追われる現役世代にとって縁遠いものと感じられている。こういった市民感情も踏まえ、自治体財政も厳しい中、市民生活に直結しない施設整備については収益性を厳しく問われることになる。
現在、シティ・トレセン構想策定に向けて総合運動公園内に滞在型交流拠点づくり、わかりやすく言えば宿泊施設の建設が検討されているが、この状況を伺う。
(1)現在、スポーツのイベントや試合、大会で市内の宿泊施設が「不足」し、近隣に宿泊客が流出しているため市内に滞在できる場所を増やしていきたいとのことだが、この不足の内容について伺う。
①どのような行事の時か。
②年間日数でいうと何日ほどか。
③曜日や時期はどうか、長期休暇以外の平日でも足りない時があるのか。
④足りない客室数はどれほどか。
⑤供給不足について、どのような調査方法で把握したか。
(2)滞在型交流拠点施設整備の担い手について
①民間活力の活用を推進するとなっているが、補助金などを利用せず100%民間の出資で建設するものか。
②民間が手を上げない場合は、市が建設するのか。
(3)施設建設が民間事業者により実現できたとしても、業績不振で短期間で撤退してしまい、結局維持管理運営を市が行うことになるということも予想される。短期間での撤退についてのペナルティ、業績不振に対する市の運営補助、改修費負担などはしないことを明確に契約すべきでないか。
標題2:市民に身近なスポーツ振興を〜スポーツを核としたまちづくり推進のために〜
(1)市民に最も身近なスポーツはウォーキング、「歩く」ことへの応援を
藤枝市スポーツ推進計画には、令和2年に市が実施した「スポーツの実施状況等に関する調査」の結果が掲載されている。
これによると、市民が「スポーツをする理由」は、「健康・体力の維持」である。一番取り組まれているスポーツはウォーキングで、以下ストレッチや体操、筋トレ、ランニング、サイクリングなど、路上や自宅で、個人で、自由な時間に道具などなくても体を動かすこと可能なものが人気上位の条件である。単に運動としてではなく、ルールに基づいて勝敗や記録を競う競技としてのスポーツには多様な種類があるが、一種目ごとの競技人口は少ない。
一方、市民が「スポーツができなかった理由」は「仕事・家事が忙しい、面倒、高齢・病気・ケガ・金銭的余裕がない」というものである。この結果は、スポーツ庁の令和5年度「スポーツの実施状況等に関する世論調査」とも同様である。
この調査結果から、市民に身近で必要とされているスポーツ振興施策は日常生活の中での運動習慣をサポートする取り組みであることがわかる。藤枝市のスポーツ推進計画にも、4つの柱「生涯スポーツの推進」「競技スポーツの推進」「スポーツ施設等の利便性の向上」「サッカーの普及と文化の醸成」と、トップに据えられている。第一に掲げられた「生涯スポーツの推進」であるが、残念ながら広く市民全体に届いているとはいえない。原因は、週末のイベントやどこかに出かけるという形態では、忙しく余裕のない市民の生活に届かないからであろう。
全国調査では全人口中、運動・スポーツが嫌いな人は約17%、理由は「特にない、疲れる、苦手」などである。大事な点は、嫌いな人でも、健康と体力の維持のために運動をしたいと思っていることである。こういった点からも、市民生活にマッチした、スポーツ推進施策はウォーキングが最適解である。ウォーキングは、健康、環境、経済、交通の4K、体と心の健康、環境にやさしく、街中ウォーキングで経済効果もあり、歩きやすいまちづくりにもつながる。そこで、歩数で市内の店舗で使えるお買い物ポイントゲットなど、現在も同様の取り組みはあるが関係各課の連携を強めることでより強力なウォーキング応援をはかられてはどうか。
(2)「生涯スポーツの推進」を中心に置いたスポーツ推進計画を
藤枝はサッカーのまちであることは市民にとっても、全国的にも共通認識が出来上がっている。
だが、「スポーツの実施状況等に関する調査」の結果によると、この一年間にサッカーを自分がしたというのは回答者の3%程度と非常に少ない。観戦については、サッカーを見たという回答が多いが、日本代表や海外サッカーが多数で、これはおそらく現地観戦ではなくテレビかネットである。なお、観戦数が多いスポーツはプロ野球、高校野球、大相撲、マラソン・駅伝、フィギュアスケートなどみなテレビ放映されているものである。実際に出かけるまでには、ハードルが高いのである。
多くの市民にとって、スポーツが「自分の事」であるのは、健康と元気につながる「日常の運動」としてなのである。市民にとっての「スポーツを核としたまちづくり」は、特別なことではなく、誰でも体を動かしてみよう思える環境と、生活の中で運動が習慣になっていることではないだろうか。
来年度、スポーツ推進計画改訂にむけて検討が行われるが、市民が主人公のスポーツ推進計画となるよう、「生涯スポーツの推進」を計画の中心に置くこと、生活習慣として広く市民の日常の運動習慣を応援する策の強化が必要ではないだろうか。
藤枝シティ・トレセン構想は、各種スポーツ施設や地域資源を生かした本市独自のスポーツ交流戦略のことであり、スポーツを核に市内全域をフィールドに、国内外からサッカーを始め多様なスポーツ活動や交流を呼び込んで、幅広い世代が集い交流できる滞在型のまちづくりを目指すというもの。
本市がサッカーのまちとして特色あるまちづくりに取り組み、スポーツや交流が活発になることは良いことと考える。しかし、スポーツは健康や元気に大いに影響するものではあるが、生活の中での優先度は低く、大会やイベント参加は多くの高齢者や、仕事子育てに追われる現役世代にとって縁遠いものと感じられている。こういった市民感情も踏まえ、自治体財政も厳しい中、市民生活に直結しない施設整備については収益性を厳しく問われることになる。
現在、シティ・トレセン構想策定に向けて総合運動公園内に滞在型交流拠点づくり、わかりやすく言えば宿泊施設の建設が検討されているが、この状況を伺う。
(1)現在、スポーツのイベントや試合、大会で市内の宿泊施設が「不足」し、近隣に宿泊客が流出しているため市内に滞在できる場所を増やしていきたいとのことだが、この不足の内容について伺う。
①どのような行事の時か。
②年間日数でいうと何日ほどか。
③曜日や時期はどうか、長期休暇以外の平日でも足りない時があるのか。
④足りない客室数はどれほどか。
⑤供給不足について、どのような調査方法で把握したか。
(2)滞在型交流拠点施設整備の担い手について
①民間活力の活用を推進するとなっているが、補助金などを利用せず100%民間の出資で建設するものか。
②民間が手を上げない場合は、市が建設するのか。
(3)施設建設が民間事業者により実現できたとしても、業績不振で短期間で撤退してしまい、結局維持管理運営を市が行うことになるということも予想される。短期間での撤退についてのペナルティ、業績不振に対する市の運営補助、改修費負担などはしないことを明確に契約すべきでないか。
標題2:市民に身近なスポーツ振興を〜スポーツを核としたまちづくり推進のために〜
(1)市民に最も身近なスポーツはウォーキング、「歩く」ことへの応援を
藤枝市スポーツ推進計画には、令和2年に市が実施した「スポーツの実施状況等に関する調査」の結果が掲載されている。
これによると、市民が「スポーツをする理由」は、「健康・体力の維持」である。一番取り組まれているスポーツはウォーキングで、以下ストレッチや体操、筋トレ、ランニング、サイクリングなど、路上や自宅で、個人で、自由な時間に道具などなくても体を動かすこと可能なものが人気上位の条件である。単に運動としてではなく、ルールに基づいて勝敗や記録を競う競技としてのスポーツには多様な種類があるが、一種目ごとの競技人口は少ない。
一方、市民が「スポーツができなかった理由」は「仕事・家事が忙しい、面倒、高齢・病気・ケガ・金銭的余裕がない」というものである。この結果は、スポーツ庁の令和5年度「スポーツの実施状況等に関する世論調査」とも同様である。
この調査結果から、市民に身近で必要とされているスポーツ振興施策は日常生活の中での運動習慣をサポートする取り組みであることがわかる。藤枝市のスポーツ推進計画にも、4つの柱「生涯スポーツの推進」「競技スポーツの推進」「スポーツ施設等の利便性の向上」「サッカーの普及と文化の醸成」と、トップに据えられている。第一に掲げられた「生涯スポーツの推進」であるが、残念ながら広く市民全体に届いているとはいえない。原因は、週末のイベントやどこかに出かけるという形態では、忙しく余裕のない市民の生活に届かないからであろう。
全国調査では全人口中、運動・スポーツが嫌いな人は約17%、理由は「特にない、疲れる、苦手」などである。大事な点は、嫌いな人でも、健康と体力の維持のために運動をしたいと思っていることである。こういった点からも、市民生活にマッチした、スポーツ推進施策はウォーキングが最適解である。ウォーキングは、健康、環境、経済、交通の4K、体と心の健康、環境にやさしく、街中ウォーキングで経済効果もあり、歩きやすいまちづくりにもつながる。そこで、歩数で市内の店舗で使えるお買い物ポイントゲットなど、現在も同様の取り組みはあるが関係各課の連携を強めることでより強力なウォーキング応援をはかられてはどうか。
(2)「生涯スポーツの推進」を中心に置いたスポーツ推進計画を
藤枝はサッカーのまちであることは市民にとっても、全国的にも共通認識が出来上がっている。
だが、「スポーツの実施状況等に関する調査」の結果によると、この一年間にサッカーを自分がしたというのは回答者の3%程度と非常に少ない。観戦については、サッカーを見たという回答が多いが、日本代表や海外サッカーが多数で、これはおそらく現地観戦ではなくテレビかネットである。なお、観戦数が多いスポーツはプロ野球、高校野球、大相撲、マラソン・駅伝、フィギュアスケートなどみなテレビ放映されているものである。実際に出かけるまでには、ハードルが高いのである。
多くの市民にとって、スポーツが「自分の事」であるのは、健康と元気につながる「日常の運動」としてなのである。市民にとっての「スポーツを核としたまちづくり」は、特別なことではなく、誰でも体を動かしてみよう思える環境と、生活の中で運動が習慣になっていることではないだろうか。
来年度、スポーツ推進計画改訂にむけて検討が行われるが、市民が主人公のスポーツ推進計画となるよう、「生涯スポーツの推進」を計画の中心に置くこと、生活習慣として広く市民の日常の運動習慣を応援する策の強化が必要ではないだろうか。