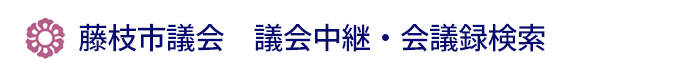質問通告内容
内容
標題1:学校にエレベーターを
(1)学校にエレベーターを
市内のある学校に通う小学生の保護者より、こんな悩みがよせられた。
「子どもが、筋ジストロフィーという筋肉が少しずつ減少していく進行性の病気にかかり、中学生になるころにはおそらく歩行が困難、車いす生活になってくると診断されている。学区の中学校には、エレベーターがない。これから病の進行に伴って、学校生活が困難になってくるので、どの学校に進学すべきか悩んでいる。自分で移動できる自由があるという点からも、ケガや障害のある方が学校に来る場合を考えても、エレベーターが必要なはず。エレベーターの設置はできないのだろうか。」という相談であった。
移動ができるかできないかということから考えれば、階段昇降機や電動車いすで事足りるが、介助の人手が必要になること、移動に時間がかかるなど、ほかの学友たちと同じようなスムーズな移動ができない。また、学校が避難所や地域拠点施設として多様な方を受け入れていくためにも、身体障害のある教員の勤務を保障していくためにもエレベーターの設置が必要とされている。
令和2年に、文部科学省が学校施設バリアフリー化推進指針改訂にともない、公立小中学校等のバリアフリー化に関する整備目標を設定している。これは、令和2年から令和7年の5年間に期間を設定し、エレベーターに関しては「既存建物を含めて要配慮児童生徒等の在籍するすべての学校に整備」というものである。また、「国の整備目標においては、バリアフリー法施行令の国土交通大臣が定める構造の昇降機を含める一方、車椅子に座ったままでは乗降できないその他の簡易的な昇降機等は含めないため、学校設置者は、このことを踏まえたエレベーターの設置を検討する必要がある」という留意事項が明記されている。
政府の方針からも、エレベーターの設置を実施していくべきではないか。
(2)学校バリアフリー計画を
現在市内のすべての市立の小中学校においては、エレベーターがない。
令和2年度、「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」(以下「バリアフリー法」)が改正され、バリアフリー法上の「特別特定建築物」に、公立小中学校等が追加された。これにより、公立小中学校等施設は、一定規模以上の建築等をするときは、バリアフリー基準への適合が義務付けられたほか、既存の建築物についてもバリアフリー基準への適合の努力義務が課せられた。
これを受けて、文部科学省では、学校施設バリアフリー化推進指針(以下「指針」)を改訂するとともに、公立小中学校等のバリアフリー化に関する整備目標を設定した。
前述したように、「令和7年度までに既存建物を含めて要配慮児童生徒等の在籍するすべての学校にエレベーターを整備」という目標があるが、場合によっては2億円程度かかるという予算の確保がネックとなり、全国的にもR7年度末見込みで32.9%と遅々として進んでいない。
その中でも静岡県の取り組みは大変遅れている。昨年9月の文部科学省の調査結果によると静岡県内での学校エレベーター設置進捗状況は14.9%と、全国平均の半分以下。47都道府県のうち44番目である。静岡県内では学校エレベーター設置が1か所もない自治体が35市町中、15市町ある。とはいえ人口7万人以上の自治体で設置がないのは本市だけである。
直近の8月22日に、文部科学省が「指針」の改定を行い令和12年までの目標として、再度「要配慮児童生徒が在籍するすべての学校にエレベーターを設置する」ことが位置付けられた。これまでの本市の方針である大規模改修や改築時に実施では、学校にエレベーターができるのはまだ10年以上先となりこの目標には間に合わず、要配慮児童生徒の在籍とも連動していない。
「指針」の改定では、すべての学校設置者がバリアフリー計画を策定することも目標に盛り込まれた。誰もが安心して学び、育つことができる教育環境を構築していくために、本市でも学校バリアフリー計画を策定し、エレベーターなどの設置をすすめていくべきではないか。
標題2:非正規公務員(会計年度任用職員)の待遇改善について 第3段
(1)任用の更新回数制限廃止を
令和2年から始まった会計年度任用職員の制度では、任用は1年契約であり、その更新は2回3年限りを原則とするものになっている。今年度は、制度導入から6年目となり、来年3月の年度末には任用されている多くの方が再び不安な公募を迎えることになる。会計年度任用職員が働くうえで最も困る、不安を感じるというのが、この次の4月からどうなるかわからないという3年目公募だ。
昨年度の11月議会で、3年目公募について「必要はないやめるべき」と取り上げた際には「検討する」という答弁があったが、残念ながら今年度の任用条件には更新回数が2回までと制限されたままである。
非正規の公務員を不安定な状態に置く、この更新回数の制限は多くの批判を浴び、昨年6月に総務省の「会計年度任用職員制度の導入等に向けた事務処理マニュアル」から削除された。これにより、全国では令和7年度の募集から更新回数の制限をなくした自治体が増えている。
自治労連の調査では、昨年12月時点で回答のあった401自治体のうち、「もともと上限なし」(25.9%)と「廃止済」(16.0%)と回答した自治体はあわせて41.9%。これに「検討中」(19.7%)と「今後検討予定」(7.7%)も合わせると69.3%、また今年4月の調査では回答のあった自治体302自治体のうち「もともと上限なし」、「廃止済」が合わせて59%とさらに増えている。東京都内に限るとすでに8割の自治体で更新の上限はなくなっている。
本市における非正規公務員の待遇改善は、給与改定の遡及においても1年の遅れをとっており、改善のペースを速める必要がある。非正規であっても安心して働けるように、また安定した市民サービスを提供するためにも、更新回数の制限は撤廃すべきではないのか。
(2)人をコスト削減の調節弁にしないこと
8月の人事院勧告により、4年連続で公務員の給与が引き上げられることとなった。
人件費上昇が続く中で、各地の自治体で人件費抑制のために、非正規公務員の任用打ち切り、日数、時間を切り詰めるなどの事例が報告されている。働く権利が守られている正規職員と違って、会計年度任用職員は1年契約3年限りという制度の問題により抗うことのできない弱い立場にある。そのため会計年度任用職員を調整弁とする事態が頻発する。
本市ではこういった事例は現時点ではないとのことであるが、人件費増大で財政が厳しくなるにつれ人員整理の圧力が強まることが予想される。そこで、来年度に向けて会計年度任用職員の任用の打ち切り、時間短縮、日数削減が検討されていないかを伺う。
(1)学校にエレベーターを
市内のある学校に通う小学生の保護者より、こんな悩みがよせられた。
「子どもが、筋ジストロフィーという筋肉が少しずつ減少していく進行性の病気にかかり、中学生になるころにはおそらく歩行が困難、車いす生活になってくると診断されている。学区の中学校には、エレベーターがない。これから病の進行に伴って、学校生活が困難になってくるので、どの学校に進学すべきか悩んでいる。自分で移動できる自由があるという点からも、ケガや障害のある方が学校に来る場合を考えても、エレベーターが必要なはず。エレベーターの設置はできないのだろうか。」という相談であった。
移動ができるかできないかということから考えれば、階段昇降機や電動車いすで事足りるが、介助の人手が必要になること、移動に時間がかかるなど、ほかの学友たちと同じようなスムーズな移動ができない。また、学校が避難所や地域拠点施設として多様な方を受け入れていくためにも、身体障害のある教員の勤務を保障していくためにもエレベーターの設置が必要とされている。
令和2年に、文部科学省が学校施設バリアフリー化推進指針改訂にともない、公立小中学校等のバリアフリー化に関する整備目標を設定している。これは、令和2年から令和7年の5年間に期間を設定し、エレベーターに関しては「既存建物を含めて要配慮児童生徒等の在籍するすべての学校に整備」というものである。また、「国の整備目標においては、バリアフリー法施行令の国土交通大臣が定める構造の昇降機を含める一方、車椅子に座ったままでは乗降できないその他の簡易的な昇降機等は含めないため、学校設置者は、このことを踏まえたエレベーターの設置を検討する必要がある」という留意事項が明記されている。
政府の方針からも、エレベーターの設置を実施していくべきではないか。
(2)学校バリアフリー計画を
現在市内のすべての市立の小中学校においては、エレベーターがない。
令和2年度、「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」(以下「バリアフリー法」)が改正され、バリアフリー法上の「特別特定建築物」に、公立小中学校等が追加された。これにより、公立小中学校等施設は、一定規模以上の建築等をするときは、バリアフリー基準への適合が義務付けられたほか、既存の建築物についてもバリアフリー基準への適合の努力義務が課せられた。
これを受けて、文部科学省では、学校施設バリアフリー化推進指針(以下「指針」)を改訂するとともに、公立小中学校等のバリアフリー化に関する整備目標を設定した。
前述したように、「令和7年度までに既存建物を含めて要配慮児童生徒等の在籍するすべての学校にエレベーターを整備」という目標があるが、場合によっては2億円程度かかるという予算の確保がネックとなり、全国的にもR7年度末見込みで32.9%と遅々として進んでいない。
その中でも静岡県の取り組みは大変遅れている。昨年9月の文部科学省の調査結果によると静岡県内での学校エレベーター設置進捗状況は14.9%と、全国平均の半分以下。47都道府県のうち44番目である。静岡県内では学校エレベーター設置が1か所もない自治体が35市町中、15市町ある。とはいえ人口7万人以上の自治体で設置がないのは本市だけである。
直近の8月22日に、文部科学省が「指針」の改定を行い令和12年までの目標として、再度「要配慮児童生徒が在籍するすべての学校にエレベーターを設置する」ことが位置付けられた。これまでの本市の方針である大規模改修や改築時に実施では、学校にエレベーターができるのはまだ10年以上先となりこの目標には間に合わず、要配慮児童生徒の在籍とも連動していない。
「指針」の改定では、すべての学校設置者がバリアフリー計画を策定することも目標に盛り込まれた。誰もが安心して学び、育つことができる教育環境を構築していくために、本市でも学校バリアフリー計画を策定し、エレベーターなどの設置をすすめていくべきではないか。
標題2:非正規公務員(会計年度任用職員)の待遇改善について 第3段
(1)任用の更新回数制限廃止を
令和2年から始まった会計年度任用職員の制度では、任用は1年契約であり、その更新は2回3年限りを原則とするものになっている。今年度は、制度導入から6年目となり、来年3月の年度末には任用されている多くの方が再び不安な公募を迎えることになる。会計年度任用職員が働くうえで最も困る、不安を感じるというのが、この次の4月からどうなるかわからないという3年目公募だ。
昨年度の11月議会で、3年目公募について「必要はないやめるべき」と取り上げた際には「検討する」という答弁があったが、残念ながら今年度の任用条件には更新回数が2回までと制限されたままである。
非正規の公務員を不安定な状態に置く、この更新回数の制限は多くの批判を浴び、昨年6月に総務省の「会計年度任用職員制度の導入等に向けた事務処理マニュアル」から削除された。これにより、全国では令和7年度の募集から更新回数の制限をなくした自治体が増えている。
自治労連の調査では、昨年12月時点で回答のあった401自治体のうち、「もともと上限なし」(25.9%)と「廃止済」(16.0%)と回答した自治体はあわせて41.9%。これに「検討中」(19.7%)と「今後検討予定」(7.7%)も合わせると69.3%、また今年4月の調査では回答のあった自治体302自治体のうち「もともと上限なし」、「廃止済」が合わせて59%とさらに増えている。東京都内に限るとすでに8割の自治体で更新の上限はなくなっている。
本市における非正規公務員の待遇改善は、給与改定の遡及においても1年の遅れをとっており、改善のペースを速める必要がある。非正規であっても安心して働けるように、また安定した市民サービスを提供するためにも、更新回数の制限は撤廃すべきではないのか。
(2)人をコスト削減の調節弁にしないこと
8月の人事院勧告により、4年連続で公務員の給与が引き上げられることとなった。
人件費上昇が続く中で、各地の自治体で人件費抑制のために、非正規公務員の任用打ち切り、日数、時間を切り詰めるなどの事例が報告されている。働く権利が守られている正規職員と違って、会計年度任用職員は1年契約3年限りという制度の問題により抗うことのできない弱い立場にある。そのため会計年度任用職員を調整弁とする事態が頻発する。
本市ではこういった事例は現時点ではないとのことであるが、人件費増大で財政が厳しくなるにつれ人員整理の圧力が強まることが予想される。そこで、来年度に向けて会計年度任用職員の任用の打ち切り、時間短縮、日数削減が検討されていないかを伺う。