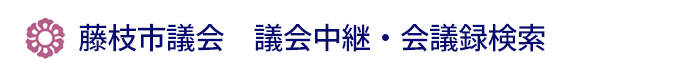質問通告内容
内容
標題1:男性育休の取得率向上を目指して
少子高齢化が進む我が国では共働き世帯が増加傾向にあり、これにより家庭内で育児や家事の負担を女性に偏らせない事が重要となっています。男性の育児休業の取得は女性の就業継続やキャリア形成を支えるだけではなく、子どもの健全な成長や家庭の安定に繋がることと考えられます。しかし、厚労省の調査では依然として男性の育児休業の取得率は低く、制度と実態に剥離があるのが現状です。
令和4年10月には育児介護休業法の改正により、「産後パパ育休(出生時育児休業)」の制度が施行されました。産後パパ育休は産後8週間以内に4週間(28日間)を限度として取得出来ること、また従来の育休制度では原則として一括取得しか出来なかったものを2分割し取得する事が出来るなど、家庭の事情に合わせながらより柔軟に育休を取得できるようになりました。加えて「パパ・ママ育休プラス」といった育児休業期間の延長に関する制度や本年4月に創設された「出生後休業支援給付金」の様に夫婦ともに通算して14日以上の育児休業取得を条件に休業中に支給される育児休業給付金を就業中の給与に対して実質手取り100%相当とする制度など、男性が育児休業をとりやすい社会環境が少しずつ整ってきています。
政府も令和7年度までに男性の育児休業取得率を50%とする事を目標としており、今後更なる制度の活用促進と周囲の理解が不可欠となって来るものと思われます。
本市でも「子育てするなら藤枝」を標語として掲げていることもあり、男性の育児休業の取得に関しては「子育てしやすいまち」としての象徴として、人口減少対策・地域ブランドの形成・男女共同参画の実践といった観点から本市にとっても戦略的に推進する価値が高い施策であると思われ、まずは本市職員の男性育休の取得率の向上を目指す事で市民に対しても男性育休のロールモデルとして提示する事が必要であると考え以下の点を伺います。
(1) 本市の男性職員の育休取得率を伺います。
(2) 男女問わず育児休業の取得に関して意識調査などは行われているのか伺います。
(3) 育児休業の取得は今後進めていく事が望ましいかとは思いますが、実際に取得者が出た際はどうしてもその分の穴埋めが必要となり周囲に負担がかかる可能性があります。この様に人員的な不足が出た際は現在どの様に対応されているのか伺います。
(4) 欧州などの事例として「パパ・クオータ制度(直訳すると父親割当制度)」といったものがあります。これは簡単に言えば「取得しないと権利が消滅する父親専用の有給休暇」といった制度であり、国内では福島県飯舘村が平成21年から導入しています。飯舘村の場合男性職員がこの制度を活用する事で配偶者の「産前1ヶ月から産後2ヶ月までの1ヶ月」の休みを取得する事ができますが、この間は研修と見なされ毎日子育て日誌を付ける事が義務づけられています。
その他の自治体においても男性育休を義務化したり管理職が 率先して育休を取るようにしたりと全国的に様々な取り組みが見られます。本市において今後の子育てしやすいまちをリードしていく事を念頭にどの様な取り組みが考えられるか、所感を伺います。
標題2:高齢者等訪問理美容サービスについて
高齢者等訪問理美容サービスは、加速する高齢化に伴い外出が困難となった高齢者や要介護者が増える中で、その生活の質を支えるために必要とされるサービスです。理美容は単に身だしなみを整える行為にとどまらず、清潔を保つことで皮膚疾患や感染症の予防につながり、心身の健康維持に寄与します。また、髪や容姿を整えることは本人の自尊心を支え、生きがいや安心感を与える大切な要素です。
さらに、訪問による理美容は施術者との会話や交流を生み出し、孤立感の解消や認知症予防といった精神的な効果も期待できます。家族や介護者にとっても、清潔保持に関わる負担が軽減され、介護全体の質が向上します。また地域社会においても、このサービスは介護保険制度の隙間を補う生活支援として位置づけられています。
現在本市においての訪問理美容サービス協力店は20店舗近くありますが、そのほとんどが理容店でありその金額設定自体「今まで店舗まで来れていたお客さんがどうしても来店自体が難しくなってしまった事に対しての奉仕の気持ちで設定した」ものであるとの事でした。このため訪問理容にかかる時間を往復の移動時間も含めて2時間と考えるとほとんどボランティアの様な価格設定となっています。この様な状況もあり5年ほど前には理容組合の藤枝支部の方から本市に対して「『紙おむつ購入助成券』や『はり・灸・マッサージ治療助成券』等と同様な『理髪助成券』の様なものの発行はできないものか?」といった声が届いているかと思います。昨今の状況を見れば当然の事ではありますが、物価の高騰や人件費の上昇で今後設定金額の見直しが必要であると考える理容店もあるようです。訪問理美容サービス協力店の中には1人で切り盛りしている店舗も見受けられ、この場合現在の価格設定である限りは訪問理容に出向く事自体のハードルが高くなっている事も事実です。
市民の生活衛生を守る一助となる訪問理美容の必要性を考えると共に今後の可能性も踏まえ以下の点を伺います。
(1) 本市における訪問理美容サービスの利用の状況、把握できているのであればその利用件数を伺います。
(2) 県内でも訪問理美容サービスに対する一部助成などの取り組みをおこなっている自治体もありますが、同様の方法においての本市で取り組む可能性はあるか伺います。
少子高齢化が進む我が国では共働き世帯が増加傾向にあり、これにより家庭内で育児や家事の負担を女性に偏らせない事が重要となっています。男性の育児休業の取得は女性の就業継続やキャリア形成を支えるだけではなく、子どもの健全な成長や家庭の安定に繋がることと考えられます。しかし、厚労省の調査では依然として男性の育児休業の取得率は低く、制度と実態に剥離があるのが現状です。
令和4年10月には育児介護休業法の改正により、「産後パパ育休(出生時育児休業)」の制度が施行されました。産後パパ育休は産後8週間以内に4週間(28日間)を限度として取得出来ること、また従来の育休制度では原則として一括取得しか出来なかったものを2分割し取得する事が出来るなど、家庭の事情に合わせながらより柔軟に育休を取得できるようになりました。加えて「パパ・ママ育休プラス」といった育児休業期間の延長に関する制度や本年4月に創設された「出生後休業支援給付金」の様に夫婦ともに通算して14日以上の育児休業取得を条件に休業中に支給される育児休業給付金を就業中の給与に対して実質手取り100%相当とする制度など、男性が育児休業をとりやすい社会環境が少しずつ整ってきています。
政府も令和7年度までに男性の育児休業取得率を50%とする事を目標としており、今後更なる制度の活用促進と周囲の理解が不可欠となって来るものと思われます。
本市でも「子育てするなら藤枝」を標語として掲げていることもあり、男性の育児休業の取得に関しては「子育てしやすいまち」としての象徴として、人口減少対策・地域ブランドの形成・男女共同参画の実践といった観点から本市にとっても戦略的に推進する価値が高い施策であると思われ、まずは本市職員の男性育休の取得率の向上を目指す事で市民に対しても男性育休のロールモデルとして提示する事が必要であると考え以下の点を伺います。
(1) 本市の男性職員の育休取得率を伺います。
(2) 男女問わず育児休業の取得に関して意識調査などは行われているのか伺います。
(3) 育児休業の取得は今後進めていく事が望ましいかとは思いますが、実際に取得者が出た際はどうしてもその分の穴埋めが必要となり周囲に負担がかかる可能性があります。この様に人員的な不足が出た際は現在どの様に対応されているのか伺います。
(4) 欧州などの事例として「パパ・クオータ制度(直訳すると父親割当制度)」といったものがあります。これは簡単に言えば「取得しないと権利が消滅する父親専用の有給休暇」といった制度であり、国内では福島県飯舘村が平成21年から導入しています。飯舘村の場合男性職員がこの制度を活用する事で配偶者の「産前1ヶ月から産後2ヶ月までの1ヶ月」の休みを取得する事ができますが、この間は研修と見なされ毎日子育て日誌を付ける事が義務づけられています。
その他の自治体においても男性育休を義務化したり管理職が 率先して育休を取るようにしたりと全国的に様々な取り組みが見られます。本市において今後の子育てしやすいまちをリードしていく事を念頭にどの様な取り組みが考えられるか、所感を伺います。
標題2:高齢者等訪問理美容サービスについて
高齢者等訪問理美容サービスは、加速する高齢化に伴い外出が困難となった高齢者や要介護者が増える中で、その生活の質を支えるために必要とされるサービスです。理美容は単に身だしなみを整える行為にとどまらず、清潔を保つことで皮膚疾患や感染症の予防につながり、心身の健康維持に寄与します。また、髪や容姿を整えることは本人の自尊心を支え、生きがいや安心感を与える大切な要素です。
さらに、訪問による理美容は施術者との会話や交流を生み出し、孤立感の解消や認知症予防といった精神的な効果も期待できます。家族や介護者にとっても、清潔保持に関わる負担が軽減され、介護全体の質が向上します。また地域社会においても、このサービスは介護保険制度の隙間を補う生活支援として位置づけられています。
現在本市においての訪問理美容サービス協力店は20店舗近くありますが、そのほとんどが理容店でありその金額設定自体「今まで店舗まで来れていたお客さんがどうしても来店自体が難しくなってしまった事に対しての奉仕の気持ちで設定した」ものであるとの事でした。このため訪問理容にかかる時間を往復の移動時間も含めて2時間と考えるとほとんどボランティアの様な価格設定となっています。この様な状況もあり5年ほど前には理容組合の藤枝支部の方から本市に対して「『紙おむつ購入助成券』や『はり・灸・マッサージ治療助成券』等と同様な『理髪助成券』の様なものの発行はできないものか?」といった声が届いているかと思います。昨今の状況を見れば当然の事ではありますが、物価の高騰や人件費の上昇で今後設定金額の見直しが必要であると考える理容店もあるようです。訪問理美容サービス協力店の中には1人で切り盛りしている店舗も見受けられ、この場合現在の価格設定である限りは訪問理容に出向く事自体のハードルが高くなっている事も事実です。
市民の生活衛生を守る一助となる訪問理美容の必要性を考えると共に今後の可能性も踏まえ以下の点を伺います。
(1) 本市における訪問理美容サービスの利用の状況、把握できているのであればその利用件数を伺います。
(2) 県内でも訪問理美容サービスに対する一部助成などの取り組みをおこなっている自治体もありますが、同様の方法においての本市で取り組む可能性はあるか伺います。