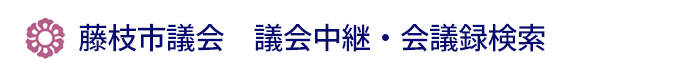質問通告内容
内容
標題1:地域計画と目標地図で浮き彫りとなった問題点と今後の課題
~新規就農者の獲得と定着に不可欠な宅地供給施策の重要性~
本市では、10地区(瀬戸谷、稲葉、葉梨、広幡、西益津・藤枝、青島、高洲、大洲、岡部、朝比奈)を対象として、農業者や農業委員、農地利用最適化推進委員、農地バンク、県農林事務所、農業協同組合等の関係機関と連携し、『農業経営基盤強化促進法』に基づく「実質化された人・農地プラン」を、令和4年2月に作成。主に中心経営体への農地の集積・集約化に焦点を当て、地域農業の担い手不足や耕作放棄地の増加といった問題を解決するための具体的な方針づくりを行いました。
その方針を踏まえ、令和5年から令和6年にかけて、各地区における地域農業の現状及び課題を拾い上げ、地域における農業の将来の在り方について、農用地等の区域の考え方や農地の効率的かつ総合的な利用、多様な経営体の確保・育成等々、多角的な事項の協議が行われ、令和6年12月に取りまとめられました。
そして令和7年3月には、各地区における地域農業の将来設計図ともいえる「地域計画」と「目標地図」が定まり公表されました。
そこで、公表された「地域計画」と「目標地図」について、次の4項目の観点から、本市農業の方向性、将来性において懸念され、深刻な問題となっている点を各地区の農地状況や意向調査から幾つか洗い出し、農地利用の最適化はもとより、新規就農者の獲得、定着に不可欠な宅地供給という両側面が推し進められることを期待し、市長及び担当部長に質問いたします。
(1)地域計画における全10地区の農地面積の状況について
① 次ページの表は、「地域計画」における農地の状況を概観するために、全10地区のデータを集計したものである。この数値から浮き彫りとなる問題を本市としてどのように捉えられ認識されているか伺う。
全10地区内の農用地等面積(農業上の利用が行われる農用地等の区域):3,667 ha
①農業振興地域のうち農用地区域内の農地面積:3,667 ha(100 %)
②田の面積:997 ha(27.2 %)
③畑の面積(果樹、茶等含む):2,670 ha(72.8 %)
④10地区内において、規模縮小などの意向のある農地面積:1,218 ha(33.2 %)
⑤10地区内において、今後農業を担う者が引き受ける意向のある農地面積:600 ha(16.4 %)
⑥10地区内における70才以上の農業者の農地面積:1,001 ha(27.3 %)
⑦ ⑥のうち後継者不在の農業者の農地面積:497 ha(13.6 %)
※アンケート調査等に非回答の農地所有者又は耕作者の農地面積:1,350 ha(36.8 %)
注)割合(%)は、全10地区内の農用地等面積の合計に対する面積率。
(2)目標地図における全10地区の現状と将来の経営面積について
① 農業を担う者の経営面積について、現状と目標年度(令和16年度)の経営面積の合計を伺う。
② 直近で市が把握している農地利用されていない遊休農地の面積はどれくらいあり、農用地区域内の農地面積(3,667ha)の何%になるか伺う。
③ 農用地の集積、集約化の取組について、現状の集積率11.1%(全10地区の平均値)に対し、将来の目標とする集積率を80%(全10地区共同じ)と明示されているが、離農者の増加や遊休農地の拡大、各地区の様態に差がある中で、一律80%を実現できるものなのか、目標集積率の根拠を含め見解と見通しを伺う。
(3)地域計画と目標地図における重点作物及び重点事業等の推進
① 本市農業の基幹作物である茶について、抹茶(碾茶)の世界的ニーズの高まりを背景に、茶業復活の兆しが見えてきているが、栽培条件が比較的良いにもかかわらず放棄された茶園の改植や更なる基盤整備の好機と考えるが見解並びに計画を伺う。
② オーガニックシティとして、事業の展開上大きな課題になっている有機栽培農地と慣行栽培農地のゾーニングや有機栽培農地の団地化について、農地バンクへの働きかけや農地所有者の合意形成、必要な基盤整備など、今後の取組施策を伺う。
③ 増加する遊休農地の解消、抑止に向けて、本市が行っている取組と成果等を伺う。
(4)地域計画の達成に向けて重要となる新規就農者への宅地供給施策
① 農業衰退の最大の原因は、若者の就農が極めて少ないことと、農振地域に移住・定住するに必須となる住居や倉庫を建築できる宅地が限られていることも背景にある。
そこで、農地の集積や集約化を推進する一方で、未利用農地の利活用策として、新規就農者が区域内に家屋・物置・車庫等を建築できる制度運用(農振除外・農地転用・建築許可)を推進するべきと考えるが見解及び可能性を伺う。
② 市街化調整区域においても、一定の要件を満たす土地であれば住宅建設を可能とする制度として「優良田園住宅」がある。ただ、敷地面積300㎡(約90坪)以上、建ぺい率最高限度3/10といった要件は、若者世帯にとって資金面や敷地管理面からハードルが高いようである。敷地面積を165㎡(約50坪)以上及び建ぺい率の緩和などを図り、就農者に限らず若者世帯の中山間地域への移住・定住促進につながる制度改正(緩和)を検討できないか伺う。
~新規就農者の獲得と定着に不可欠な宅地供給施策の重要性~
本市では、10地区(瀬戸谷、稲葉、葉梨、広幡、西益津・藤枝、青島、高洲、大洲、岡部、朝比奈)を対象として、農業者や農業委員、農地利用最適化推進委員、農地バンク、県農林事務所、農業協同組合等の関係機関と連携し、『農業経営基盤強化促進法』に基づく「実質化された人・農地プラン」を、令和4年2月に作成。主に中心経営体への農地の集積・集約化に焦点を当て、地域農業の担い手不足や耕作放棄地の増加といった問題を解決するための具体的な方針づくりを行いました。
その方針を踏まえ、令和5年から令和6年にかけて、各地区における地域農業の現状及び課題を拾い上げ、地域における農業の将来の在り方について、農用地等の区域の考え方や農地の効率的かつ総合的な利用、多様な経営体の確保・育成等々、多角的な事項の協議が行われ、令和6年12月に取りまとめられました。
そして令和7年3月には、各地区における地域農業の将来設計図ともいえる「地域計画」と「目標地図」が定まり公表されました。
そこで、公表された「地域計画」と「目標地図」について、次の4項目の観点から、本市農業の方向性、将来性において懸念され、深刻な問題となっている点を各地区の農地状況や意向調査から幾つか洗い出し、農地利用の最適化はもとより、新規就農者の獲得、定着に不可欠な宅地供給という両側面が推し進められることを期待し、市長及び担当部長に質問いたします。
(1)地域計画における全10地区の農地面積の状況について
① 次ページの表は、「地域計画」における農地の状況を概観するために、全10地区のデータを集計したものである。この数値から浮き彫りとなる問題を本市としてどのように捉えられ認識されているか伺う。
全10地区内の農用地等面積(農業上の利用が行われる農用地等の区域):3,667 ha
①農業振興地域のうち農用地区域内の農地面積:3,667 ha(100 %)
②田の面積:997 ha(27.2 %)
③畑の面積(果樹、茶等含む):2,670 ha(72.8 %)
④10地区内において、規模縮小などの意向のある農地面積:1,218 ha(33.2 %)
⑤10地区内において、今後農業を担う者が引き受ける意向のある農地面積:600 ha(16.4 %)
⑥10地区内における70才以上の農業者の農地面積:1,001 ha(27.3 %)
⑦ ⑥のうち後継者不在の農業者の農地面積:497 ha(13.6 %)
※アンケート調査等に非回答の農地所有者又は耕作者の農地面積:1,350 ha(36.8 %)
注)割合(%)は、全10地区内の農用地等面積の合計に対する面積率。
(2)目標地図における全10地区の現状と将来の経営面積について
① 農業を担う者の経営面積について、現状と目標年度(令和16年度)の経営面積の合計を伺う。
② 直近で市が把握している農地利用されていない遊休農地の面積はどれくらいあり、農用地区域内の農地面積(3,667ha)の何%になるか伺う。
③ 農用地の集積、集約化の取組について、現状の集積率11.1%(全10地区の平均値)に対し、将来の目標とする集積率を80%(全10地区共同じ)と明示されているが、離農者の増加や遊休農地の拡大、各地区の様態に差がある中で、一律80%を実現できるものなのか、目標集積率の根拠を含め見解と見通しを伺う。
(3)地域計画と目標地図における重点作物及び重点事業等の推進
① 本市農業の基幹作物である茶について、抹茶(碾茶)の世界的ニーズの高まりを背景に、茶業復活の兆しが見えてきているが、栽培条件が比較的良いにもかかわらず放棄された茶園の改植や更なる基盤整備の好機と考えるが見解並びに計画を伺う。
② オーガニックシティとして、事業の展開上大きな課題になっている有機栽培農地と慣行栽培農地のゾーニングや有機栽培農地の団地化について、農地バンクへの働きかけや農地所有者の合意形成、必要な基盤整備など、今後の取組施策を伺う。
③ 増加する遊休農地の解消、抑止に向けて、本市が行っている取組と成果等を伺う。
(4)地域計画の達成に向けて重要となる新規就農者への宅地供給施策
① 農業衰退の最大の原因は、若者の就農が極めて少ないことと、農振地域に移住・定住するに必須となる住居や倉庫を建築できる宅地が限られていることも背景にある。
そこで、農地の集積や集約化を推進する一方で、未利用農地の利活用策として、新規就農者が区域内に家屋・物置・車庫等を建築できる制度運用(農振除外・農地転用・建築許可)を推進するべきと考えるが見解及び可能性を伺う。
② 市街化調整区域においても、一定の要件を満たす土地であれば住宅建設を可能とする制度として「優良田園住宅」がある。ただ、敷地面積300㎡(約90坪)以上、建ぺい率最高限度3/10といった要件は、若者世帯にとって資金面や敷地管理面からハードルが高いようである。敷地面積を165㎡(約50坪)以上及び建ぺい率の緩和などを図り、就農者に限らず若者世帯の中山間地域への移住・定住促進につながる制度改正(緩和)を検討できないか伺う。