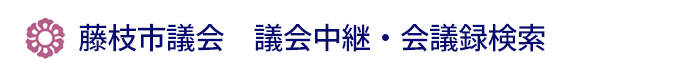質問通告内容
内容
標題1:当初予算「スクラップ&ビルド」編成過程
(1)将来の負担増を見越して、今年度予算編成の柱の一つに「選択と集中による徹底した事業のスクラップ&ビルド」(全事業総点検シートによる市民目線、市民感覚に基づく事業の点検の見直し)が掲げている。
昨年度予算化されながら、今年度予算措置されなかったのは82事業あるが、予算の組み換えや事業終了などを除いて、廃止となった事業はいくつあるか。
(2)単独事業ではないが、廃止された住民サービスとして敬老祝い金(75歳に5000円支給、約1100万円)や広報ふじえだ発行回数月2回から月1回へ、約1600万円)の他、多子世帯子育て応援事業(中学生以下の子ども3人以上の世帯に対し、市内施設入場料の減免、約500万円)がある。延べ13375人が利用しているが、市民感覚に基づく廃止の決断の根拠は何か。
(3)同事業は、過去の議会質問で実現した制度でありながら、予算審議の過程で何ら議会に説明なく廃止された。私は、普段利用している大洲のプールで偶然知ったが、議会で議論を重ねてきた制度については、少なくとも知らせる必要があるのではないか。
標題2:県民市民不在のリニア。水問題の対話は完了していない。
6月2日、県とJR東海と間で続けられてきた6項目の水問題の対話が完了し、知事は「(水問題という)大きな山は越えた。これからもできるだけ短縮できるように努力したい」平木副知事は「水資源に関する対話の終了は大きな一歩だ。丁寧かつスピード感を持って一歩一歩、段階を踏んでおり、残りの対話項目についても丁寧にきめ細かくやっていきたい」と述べ、残る生物多様性、残土がクリアー出来れば工事着手を許可するかのような言葉を述べている。
知事が交代した事によって、これまでの「水は一滴も減らさない」という県の立場が大きく後退している現状で、当事者としての流域自治体の立場が問われる。
北村市長は知識も経験も豊富であり、これまでの市議会でもかみ合った議論が出来てきたと感じているが、今こそ頑張り時だと考える。
(1)現状は、県境の高速長尺ボーリングが失敗したため、山梨県側から先進坑の工事が毎日1m程度掘り進められており、その過程で県境手前の断層調査(コアボーリング)を行う事が11月の予定、県境越えの西俣断層の大破砕帯に5本ものトンネルを掘る人類が経験した事のない大工事はこれからであり、”山を越えた”だの”転換期を迎えた”だの水問題が解決したかのような印象操作が行われていると考えるが、市長の認識はどうか。
(2)専門部会の議論は、今後工事を進めるに当たっての「管理フロー」を合意しただけであり、その中には成功の可能性が低い「薬液注入」を含む上に、予測以上の湧水量が発生した場合「田代ダムにおける取水抑制の可否の判断」も含まれる。そもそもの工事着手の出発点である毎秒2㌧そのものの見直しもあり得る「管理フロー」となっている。専門部会自体はこれで終了したわけでもない。これで“対話完了”と言えるのか。
(3)7月27日、JR東海と10市町首長と非公開の意見交換会が行われ、JRから対話完了の報告があり、この場でJRからどれだけの説明がなされ、市長自身は納得されているか。
(4)JR東海社長は「静岡工区の1日も早い着工が出来るよう10市町の理解を得られるよう深めていきたい」と述べ、島田市長は「何度も対話を重ねてきてお互いの理解や信頼が深まった」と応えているが県民市民には全く中身が知らされておらず、理解も信頼も深まっていない。
今秋、住民説明会の実施を了承しているが、そもそも、説明を受けるのであれば県から先に受けるべきであり、この状況下で説明会をやってもJRに都合の良い内容になるだけではないか。流域自治体がやるべき事は、正確な情報を市民に知らせる事ではないか。
(1)将来の負担増を見越して、今年度予算編成の柱の一つに「選択と集中による徹底した事業のスクラップ&ビルド」(全事業総点検シートによる市民目線、市民感覚に基づく事業の点検の見直し)が掲げている。
昨年度予算化されながら、今年度予算措置されなかったのは82事業あるが、予算の組み換えや事業終了などを除いて、廃止となった事業はいくつあるか。
(2)単独事業ではないが、廃止された住民サービスとして敬老祝い金(75歳に5000円支給、約1100万円)や広報ふじえだ発行回数月2回から月1回へ、約1600万円)の他、多子世帯子育て応援事業(中学生以下の子ども3人以上の世帯に対し、市内施設入場料の減免、約500万円)がある。延べ13375人が利用しているが、市民感覚に基づく廃止の決断の根拠は何か。
(3)同事業は、過去の議会質問で実現した制度でありながら、予算審議の過程で何ら議会に説明なく廃止された。私は、普段利用している大洲のプールで偶然知ったが、議会で議論を重ねてきた制度については、少なくとも知らせる必要があるのではないか。
標題2:県民市民不在のリニア。水問題の対話は完了していない。
6月2日、県とJR東海と間で続けられてきた6項目の水問題の対話が完了し、知事は「(水問題という)大きな山は越えた。これからもできるだけ短縮できるように努力したい」平木副知事は「水資源に関する対話の終了は大きな一歩だ。丁寧かつスピード感を持って一歩一歩、段階を踏んでおり、残りの対話項目についても丁寧にきめ細かくやっていきたい」と述べ、残る生物多様性、残土がクリアー出来れば工事着手を許可するかのような言葉を述べている。
知事が交代した事によって、これまでの「水は一滴も減らさない」という県の立場が大きく後退している現状で、当事者としての流域自治体の立場が問われる。
北村市長は知識も経験も豊富であり、これまでの市議会でもかみ合った議論が出来てきたと感じているが、今こそ頑張り時だと考える。
(1)現状は、県境の高速長尺ボーリングが失敗したため、山梨県側から先進坑の工事が毎日1m程度掘り進められており、その過程で県境手前の断層調査(コアボーリング)を行う事が11月の予定、県境越えの西俣断層の大破砕帯に5本ものトンネルを掘る人類が経験した事のない大工事はこれからであり、”山を越えた”だの”転換期を迎えた”だの水問題が解決したかのような印象操作が行われていると考えるが、市長の認識はどうか。
(2)専門部会の議論は、今後工事を進めるに当たっての「管理フロー」を合意しただけであり、その中には成功の可能性が低い「薬液注入」を含む上に、予測以上の湧水量が発生した場合「田代ダムにおける取水抑制の可否の判断」も含まれる。そもそもの工事着手の出発点である毎秒2㌧そのものの見直しもあり得る「管理フロー」となっている。専門部会自体はこれで終了したわけでもない。これで“対話完了”と言えるのか。
(3)7月27日、JR東海と10市町首長と非公開の意見交換会が行われ、JRから対話完了の報告があり、この場でJRからどれだけの説明がなされ、市長自身は納得されているか。
(4)JR東海社長は「静岡工区の1日も早い着工が出来るよう10市町の理解を得られるよう深めていきたい」と述べ、島田市長は「何度も対話を重ねてきてお互いの理解や信頼が深まった」と応えているが県民市民には全く中身が知らされておらず、理解も信頼も深まっていない。
今秋、住民説明会の実施を了承しているが、そもそも、説明を受けるのであれば県から先に受けるべきであり、この状況下で説明会をやってもJRに都合の良い内容になるだけではないか。流域自治体がやるべき事は、正確な情報を市民に知らせる事ではないか。