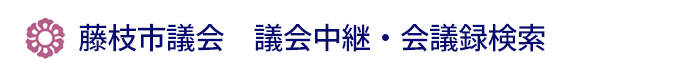質問通告内容
内容
標題1:兵太夫中地区の水路氾濫対策
台風15号による豪雨で、市内各地で水害が発生した。
水路が複雑な兵太夫中地区は、宅地化による遊水地機能がなくなるなどで、かねてより水路氾濫が発生、今回も床上浸水を含む広範な範囲で被害が発生した。
私も2日間かけて地域の声を聞いたが、幸いにも豪雨時間が短かく、命に関わる事態は起こらなかったが、後30分続けば高齢者はどうしようもなかったなど、深刻な声を聴いた。
平成25年11月議会で、当該箇所の対策を求め、市長自ら現地で調査してくださった。排水幹線黒石川の河口部からの改修が抜本的であるが、この先何十年かかるか見通しが立たない中で、「遊水地機能がなくなったことによる調整池を含めた排水系統の対策」が示され、一定の対策が取られた。
しかし、近年の降雨は、かつてない規模になり、この対策が必ずしも地域住民の安心感を得られていないと考える。
過去の対応が、今も有効かどうかを含め、地元を交えた改修策の新たな検討が必要ではないか。
標題2:中心市街地再開発事業(住民と一体となった街づくりで、BiViの再興など)
各地で再開発事業が行われているが、大きなつまづきに直面しており、許可件数は2000年以降かつての10分の1に減り、中野サンプラザなどの破たんも明らかになっている。
巨額の公費を使う駅近くの高層ビルは、市民の目につき関心も高く、建設経済環境委員会では今年度の調査項目とした。
既に駅北9街区は令和9年竣工に向け建設中であり、6街区は都市計画決定済みであるが、これまでの経緯から、今後の地域づくりがどうあるべきか。
(1)そもそもの出発点が住民主導であるかどうかが街の再生には不可欠だと考えるが、準備組合結成前の「まちづくり会議」等において、デベロッパーである穴吹興産㈱(9街区)、静岡鉄道㈱及び㈱フージャースコーポレーションの位置づけはどうだったのか。(基本計画等はだれが作ったのかなど)
(2)再開発の都市計画決定に対し、3分の1の反対があっても事業が行える特例があるが、9街区12名、6街区10名以外に、地権者でありながら組合に入らない、もしくは、都市計画に反対した地権者はあったのか。あれば何人か。
(3)再開発で生みだされたビルの床のうち、その大部分を占める保留床の売却で不動産デベロッパーが公費補助の元多額の利益を得る事になるが、権利者のものである権利床と、商業部分となる保留床、住宅販売部分となる保留床の延べ床面積はどれほどか。(9街区)
(4)再開発前の土地の、従前地価及び従前建物の平均床原価(9街区)
(5)将来、工事費や人件費の増額によってゼネコンから増額の要求が出た場合、特定業務代行者として既にゼネコンが組合に参画している(9街区:鉄建建設㈱、6街区鉄建建設㈱、㈱ユーデーコンサルタンツ)が、その場合の対応はどうなるのか。
(6)視察先進地では、ビルの建設だけではなく、周辺のにぎわい創出の取組が併せて行われていた。本市でも実施しているものの、イベント来場者数や昼間の歩行者通行量の数値は減少している。官主導ではなく、公民連携の多面的展開をすべきではないか。
(7)駅南のBiViについては、空きテナントが多く、市民の関心は一際大きい。昨年6月議会の大石心平議員の質問で、約3年後の定期借地権の延長は明らかになった。
今後、官民連携で新たな拠点とする方針が示されているが、本来は商業施設として、大和リースへの賃料は民間事業者より行うはずだった。
空きテナント対策として、全国で市役所の出先機関などを充てる事で体裁が整えられているが、新たな税負担が生じたり、テナントを埋めるために事業を立ち上げなどが行われている。これまで民間事業者の出店促進など取組はどうであり、あくまでも民間事業所の出店を追求すべきではないのか。
台風15号による豪雨で、市内各地で水害が発生した。
水路が複雑な兵太夫中地区は、宅地化による遊水地機能がなくなるなどで、かねてより水路氾濫が発生、今回も床上浸水を含む広範な範囲で被害が発生した。
私も2日間かけて地域の声を聞いたが、幸いにも豪雨時間が短かく、命に関わる事態は起こらなかったが、後30分続けば高齢者はどうしようもなかったなど、深刻な声を聴いた。
平成25年11月議会で、当該箇所の対策を求め、市長自ら現地で調査してくださった。排水幹線黒石川の河口部からの改修が抜本的であるが、この先何十年かかるか見通しが立たない中で、「遊水地機能がなくなったことによる調整池を含めた排水系統の対策」が示され、一定の対策が取られた。
しかし、近年の降雨は、かつてない規模になり、この対策が必ずしも地域住民の安心感を得られていないと考える。
過去の対応が、今も有効かどうかを含め、地元を交えた改修策の新たな検討が必要ではないか。
標題2:中心市街地再開発事業(住民と一体となった街づくりで、BiViの再興など)
各地で再開発事業が行われているが、大きなつまづきに直面しており、許可件数は2000年以降かつての10分の1に減り、中野サンプラザなどの破たんも明らかになっている。
巨額の公費を使う駅近くの高層ビルは、市民の目につき関心も高く、建設経済環境委員会では今年度の調査項目とした。
既に駅北9街区は令和9年竣工に向け建設中であり、6街区は都市計画決定済みであるが、これまでの経緯から、今後の地域づくりがどうあるべきか。
(1)そもそもの出発点が住民主導であるかどうかが街の再生には不可欠だと考えるが、準備組合結成前の「まちづくり会議」等において、デベロッパーである穴吹興産㈱(9街区)、静岡鉄道㈱及び㈱フージャースコーポレーションの位置づけはどうだったのか。(基本計画等はだれが作ったのかなど)
(2)再開発の都市計画決定に対し、3分の1の反対があっても事業が行える特例があるが、9街区12名、6街区10名以外に、地権者でありながら組合に入らない、もしくは、都市計画に反対した地権者はあったのか。あれば何人か。
(3)再開発で生みだされたビルの床のうち、その大部分を占める保留床の売却で不動産デベロッパーが公費補助の元多額の利益を得る事になるが、権利者のものである権利床と、商業部分となる保留床、住宅販売部分となる保留床の延べ床面積はどれほどか。(9街区)
(4)再開発前の土地の、従前地価及び従前建物の平均床原価(9街区)
(5)将来、工事費や人件費の増額によってゼネコンから増額の要求が出た場合、特定業務代行者として既にゼネコンが組合に参画している(9街区:鉄建建設㈱、6街区鉄建建設㈱、㈱ユーデーコンサルタンツ)が、その場合の対応はどうなるのか。
(6)視察先進地では、ビルの建設だけではなく、周辺のにぎわい創出の取組が併せて行われていた。本市でも実施しているものの、イベント来場者数や昼間の歩行者通行量の数値は減少している。官主導ではなく、公民連携の多面的展開をすべきではないか。
(7)駅南のBiViについては、空きテナントが多く、市民の関心は一際大きい。昨年6月議会の大石心平議員の質問で、約3年後の定期借地権の延長は明らかになった。
今後、官民連携で新たな拠点とする方針が示されているが、本来は商業施設として、大和リースへの賃料は民間事業者より行うはずだった。
空きテナント対策として、全国で市役所の出先機関などを充てる事で体裁が整えられているが、新たな税負担が生じたり、テナントを埋めるために事業を立ち上げなどが行われている。これまで民間事業者の出店促進など取組はどうであり、あくまでも民間事業所の出店を追求すべきではないのか。