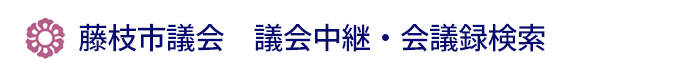質問通告内容
内容
標題1:これから求められる移動ニーズと地域交通政策の今後の展開について
今年度、藤枝市地域公共交通計画は、新たに令和8年度から12年度までの5か年計画の策定作業を進めています。近年、燃料費や人件費の高騰により公共交通の維持経費は増加し、財政負担も大きくなっています。また、いわゆる「2024年問題」とされる運転手の人材不足も重なり、公共交通の維持が難しくなっている現状があります。
一方で、「移動の不安」を抱える市民の声は年々増えています。公共交通は、単なる移動手段ではなく、暮らしを支える生活インフラとして、その重要性が一層高まっています。特に、高齢化の進行によりマイカーに頼れない人が増える中、“誰もが安心して移動できる環境”を守ることは、これからの行政の大きな使命であると感じます。
そこで、これから求められる移動ニーズと、地域交通政策の今後の展開について、以下の点を伺います。
(1) ここ数年、バス停型乗合タクシーの延伸や新規路線の運行など、取組が進み一定の成果が見られます。一方で、停留所までの距離や乗り換えの不便さなど、地域によって使いづらさも残っています。
現行計画の5か年を振り返り、市としての成果と課題、また市民の意見を次期計画へどのように反映していくのか伺います。
(2) 公共交通の維持費は年々増加し、燃料費や人件費の高騰、運転手不足などにより、今後も厳しい状況が続くと見込まれます。一方で、高齢化の進行により公共交通へのニーズは高まっています。財政負担の増加を理由に縮小するのではなく、持続可能な交通体系をどのように確立していくのか伺います。
(3) 本市では、市が主体となった取組や民間事業者による実証実験が行われてきました。
これらの実験を通じて得られた成果や課題をどのように整理し、次期地域公共交通計画にどのように活かしていくのか伺います。
(4) まちづくりの進展や高齢化の進行により、地域の移動ニーズは多様化しています。
買い物や通院など日常生活に密着した移動の確保が重要となる中、地域の実情に合わせたきめ細かく柔軟な交通ネットワークをどのように整備していくのか伺います。
標題2:介護予防の推進と人材育成について
藤枝市は「健康・予防日本一」を掲げ、健康づくりや認知症対策などに積極的に取り組み、先進地として注目されてきました。特に、住民主体の「ふじえだアクティブクラブ」を創設し、グループ活動を通して高齢者が活動的に交流する機会を生み出したことで、要介護認定率が国平均と比較して低く推移している点は、本市の大きな成果であります。
また、介護が必要となっても住み慣れた地域で安心して暮らせるよう、地域包括ケアシステムを先進的に構築し、志太医師会と連携して在宅医療サポートセンターを立ち上げるなど、医療と介護の連携体制を強化してきました。このように、健康づくりから在宅支援までを一体的に進めてきたことは、本市の特長であり誇るべき取組であります。
一方で、健康と介護の“間”にあたる「介護予防」、すなわち要介護状態になることを防ぎ、生活の自立を支える仕組みづくりは、今後さらに重要となります。介護予防は、本人の幸せや家族の安心を守るだけでなく、介護保険制度を持続可能にするための要ともいえる取組であります。
しかし、介護予防に必要な人材や地域支援の担い手不足、通いの場やサロン活動の継続など、地域によって課題も見られます。
これまで積み重ねてきた取組をさらに充実・発展させ、地域活動を基盤にした個別支援へとつなげていくことが求められます。そこで今後の取り組みについて以下伺います。
(1) 高齢者の外出や交流機会の減少、通いの場の活動低下、担い手不足などが課題となる中、現状の成果と課題をどのように分析しているか。これまでの健康づくりや介護予防の取組を踏まえ、今後どのように介護予防を深化させていくのか、その重点の方向性を伺います。
(2) 地域活動の継続と個別支援を両立させることが、今後の介護予防の推進において重要と考えます。地域包括支援センターや生活支援コーディネーターとの連携をどのように強化し、個々の高齢者の状態に応じた支援体制をどのように整えていくのか伺います。
今年度、藤枝市地域公共交通計画は、新たに令和8年度から12年度までの5か年計画の策定作業を進めています。近年、燃料費や人件費の高騰により公共交通の維持経費は増加し、財政負担も大きくなっています。また、いわゆる「2024年問題」とされる運転手の人材不足も重なり、公共交通の維持が難しくなっている現状があります。
一方で、「移動の不安」を抱える市民の声は年々増えています。公共交通は、単なる移動手段ではなく、暮らしを支える生活インフラとして、その重要性が一層高まっています。特に、高齢化の進行によりマイカーに頼れない人が増える中、“誰もが安心して移動できる環境”を守ることは、これからの行政の大きな使命であると感じます。
そこで、これから求められる移動ニーズと、地域交通政策の今後の展開について、以下の点を伺います。
(1) ここ数年、バス停型乗合タクシーの延伸や新規路線の運行など、取組が進み一定の成果が見られます。一方で、停留所までの距離や乗り換えの不便さなど、地域によって使いづらさも残っています。
現行計画の5か年を振り返り、市としての成果と課題、また市民の意見を次期計画へどのように反映していくのか伺います。
(2) 公共交通の維持費は年々増加し、燃料費や人件費の高騰、運転手不足などにより、今後も厳しい状況が続くと見込まれます。一方で、高齢化の進行により公共交通へのニーズは高まっています。財政負担の増加を理由に縮小するのではなく、持続可能な交通体系をどのように確立していくのか伺います。
(3) 本市では、市が主体となった取組や民間事業者による実証実験が行われてきました。
これらの実験を通じて得られた成果や課題をどのように整理し、次期地域公共交通計画にどのように活かしていくのか伺います。
(4) まちづくりの進展や高齢化の進行により、地域の移動ニーズは多様化しています。
買い物や通院など日常生活に密着した移動の確保が重要となる中、地域の実情に合わせたきめ細かく柔軟な交通ネットワークをどのように整備していくのか伺います。
標題2:介護予防の推進と人材育成について
藤枝市は「健康・予防日本一」を掲げ、健康づくりや認知症対策などに積極的に取り組み、先進地として注目されてきました。特に、住民主体の「ふじえだアクティブクラブ」を創設し、グループ活動を通して高齢者が活動的に交流する機会を生み出したことで、要介護認定率が国平均と比較して低く推移している点は、本市の大きな成果であります。
また、介護が必要となっても住み慣れた地域で安心して暮らせるよう、地域包括ケアシステムを先進的に構築し、志太医師会と連携して在宅医療サポートセンターを立ち上げるなど、医療と介護の連携体制を強化してきました。このように、健康づくりから在宅支援までを一体的に進めてきたことは、本市の特長であり誇るべき取組であります。
一方で、健康と介護の“間”にあたる「介護予防」、すなわち要介護状態になることを防ぎ、生活の自立を支える仕組みづくりは、今後さらに重要となります。介護予防は、本人の幸せや家族の安心を守るだけでなく、介護保険制度を持続可能にするための要ともいえる取組であります。
しかし、介護予防に必要な人材や地域支援の担い手不足、通いの場やサロン活動の継続など、地域によって課題も見られます。
これまで積み重ねてきた取組をさらに充実・発展させ、地域活動を基盤にした個別支援へとつなげていくことが求められます。そこで今後の取り組みについて以下伺います。
(1) 高齢者の外出や交流機会の減少、通いの場の活動低下、担い手不足などが課題となる中、現状の成果と課題をどのように分析しているか。これまでの健康づくりや介護予防の取組を踏まえ、今後どのように介護予防を深化させていくのか、その重点の方向性を伺います。
(2) 地域活動の継続と個別支援を両立させることが、今後の介護予防の推進において重要と考えます。地域包括支援センターや生活支援コーディネーターとの連携をどのように強化し、個々の高齢者の状態に応じた支援体制をどのように整えていくのか伺います。