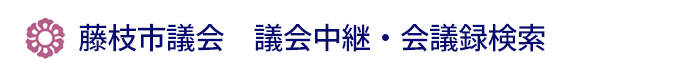質問通告内容
内容
標題1:新年度からの個別計画(案)に関連して
藤枝市では現在、第6次総合計画に基づいて各種事業が推進されており、10年間の総合計画期間のうち令和7年度は5年目となることから後期の5年目のスタートとなる令和8年度に向けて計画の改訂作業が行われており、総合計画の下に位置する各種の個別計画も同じタイミングで見直しが行われています。
多くの計画やビジョン・プランの策定作業が行われていますが、今回は「第6次藤枝市地域福祉計画・地域福祉活動計画(案)」の中の「重層的支援体制整備事業実施計画(案)」と「藤枝市耐震改修促進計画(案)」に関連して確認も含め伺います。
(1)重層的支援体制整備事業実施計画(案)に関連して
①重層的支援体制整備事業について
重層的支援体制整備事業については、令和2年11月定例月議会で山本信行議員が一般質問をしています。その際には「生活困窮者の現状と課題について」という標題の6点目として、「継続して寄り添う伴奏型支援や、いわゆる断らない相談支援体制を具体化するための重層的支援体制整備事業を含む改正社会福祉法が来年4月に施行される。改正社会福祉法について、本市の考え方を伺う。」というものでした。
この質問については市長から答弁をしていただいていますが、重層的支援体制整備事業計画は初めての策定になりますので、取り組むにあたってのご所見を伺います。
②質問後の対応について
重層的支援体制整備事業の実施は努力義務ではありましたが、今回、地域福祉計画と一体的に策定されることは喜ばしいと感じております。
この事業への取り組みについて令和2年の質問に対して「国の施策を注視し」と答弁されておられた様に、国や県の動向も影響してきますが山本議員の質問以降、事業開始に向けた検討状況について伺います。
③重層的支援体制整備事業への課題について
課題についても令和2年での質問で一部やり取りがあったところですが、特に本年度は国や県も事業への取り組みに力を入れ始めたとの印象を持っております。しかし、実際に取り組む最前線の地方自治体にとっては、それぞれの自治体で課題もあるところですので、本事業を推進するについての本市における課題について改めて伺います。
④推進体制について
重層的支援体制整備事業は「属性を問わない支援」「参加支援」「地域づくりに向けた支援」の3つの支援を一体的に実施する事業とされています。
この事業では多くの関係機関の連携が不可欠だと思いますが、司令塔となる部署を含め推進体制について伺います。
(2)藤枝市耐震改修促進計画(案)に関連して
藤枝市では、耐震化に関わる計画である現在の「藤枝市耐震改修促進計画」が本年度に最終年度を迎えることから、令和8年度から始まる次期「藤枝市耐震改修促進計画」の改訂を現在進められておりますが以下3点について伺います。
①耐震化率について
市が推進している「わが家の地震対策3本柱(住宅の耐震化・家具の転倒防止・非常用品の準備)」のうち、「木造住宅の耐震化」については市民の命を守る重要な施策ですが、旧耐震基準である昭和56年5月以前の木造住宅の藤枝市の耐震化率と、県および近隣市の耐震化率の状況について伺います。
併せて、新耐震基準であっても平成12年(2000年)基準を満たしていない木造住宅の状況について伺います。
②代理受領制度について
住宅の耐震化を進める上では費用面が大きな課題になります。私は「補助金は出ても、一旦業者には全額を支払うので、その点で足踏みをしている。」という声を市民からいただいておりました。
市の担当部署とは何度か意見交換をしてきたところですが、その様な中、次期計画(案)では、新たな取り組みの一つに代理受領制度を位置付けていますので、制度の詳細と実施時期を伺います。
③補助金の増額について
木造住宅の耐震改修には多額の費用が掛かることから、その費用面が理由で耐震改修工事に踏み切れない市民は現実におられます。
補助の上限額を時限的に引き上げて耐震化を推進している自治体もありますが、藤枝市においても補助上限額の拡充を検討できないか伺います。
標題2:奨学金返還への支援について
(1)利用状況と評価について
本市における奨学金の返還支援については、市内の金融機関にご協力をしていただいている「Uターン・地元就職応援プロジェクト」の奨学ローンや奨励金があります。
金融機関との連携協定の調印は令和3年度の途中でしたが事業開始後の利用状況の推移と、地元就職という観点からどのように評価をされているのか伺います。
(2)中小企業向け奨学金返還支援制度について
本年11月3日の静岡新聞6面のコラムで淑徳大学の結城康博教授は、『最近の大学生の約55%は何らかの奨学金を借りており、就職してから奨学金の返済が始まっていくため、学生が就職先を選ぶポイントとして、「賃金」「研修体制」「キャリアビジョン」など以外に、奨学金返済「手当」があるかを確認する学生が増えている。』と述べ、さらに『奨学金の肩代わりは、対外的に若者支援に取り組んでいるといった企業イメージにもつながり、かなり効果的な方策ではないだろうか。』と文章を結ばれています。
さて、本年度の途中から県では「中小企業等奨学金返還支援制度」を始めました。この制度は県・市町・中小企業等が連携をして取り組むことを前提としており、県としても連携する市町を増やしていきたいとの意向がある様です。
そこで、本市としては来年度当初からのタイミングで開始をしていくことは出来ないか、お考えを伺います。
藤枝市では現在、第6次総合計画に基づいて各種事業が推進されており、10年間の総合計画期間のうち令和7年度は5年目となることから後期の5年目のスタートとなる令和8年度に向けて計画の改訂作業が行われており、総合計画の下に位置する各種の個別計画も同じタイミングで見直しが行われています。
多くの計画やビジョン・プランの策定作業が行われていますが、今回は「第6次藤枝市地域福祉計画・地域福祉活動計画(案)」の中の「重層的支援体制整備事業実施計画(案)」と「藤枝市耐震改修促進計画(案)」に関連して確認も含め伺います。
(1)重層的支援体制整備事業実施計画(案)に関連して
①重層的支援体制整備事業について
重層的支援体制整備事業については、令和2年11月定例月議会で山本信行議員が一般質問をしています。その際には「生活困窮者の現状と課題について」という標題の6点目として、「継続して寄り添う伴奏型支援や、いわゆる断らない相談支援体制を具体化するための重層的支援体制整備事業を含む改正社会福祉法が来年4月に施行される。改正社会福祉法について、本市の考え方を伺う。」というものでした。
この質問については市長から答弁をしていただいていますが、重層的支援体制整備事業計画は初めての策定になりますので、取り組むにあたってのご所見を伺います。
②質問後の対応について
重層的支援体制整備事業の実施は努力義務ではありましたが、今回、地域福祉計画と一体的に策定されることは喜ばしいと感じております。
この事業への取り組みについて令和2年の質問に対して「国の施策を注視し」と答弁されておられた様に、国や県の動向も影響してきますが山本議員の質問以降、事業開始に向けた検討状況について伺います。
③重層的支援体制整備事業への課題について
課題についても令和2年での質問で一部やり取りがあったところですが、特に本年度は国や県も事業への取り組みに力を入れ始めたとの印象を持っております。しかし、実際に取り組む最前線の地方自治体にとっては、それぞれの自治体で課題もあるところですので、本事業を推進するについての本市における課題について改めて伺います。
④推進体制について
重層的支援体制整備事業は「属性を問わない支援」「参加支援」「地域づくりに向けた支援」の3つの支援を一体的に実施する事業とされています。
この事業では多くの関係機関の連携が不可欠だと思いますが、司令塔となる部署を含め推進体制について伺います。
(2)藤枝市耐震改修促進計画(案)に関連して
藤枝市では、耐震化に関わる計画である現在の「藤枝市耐震改修促進計画」が本年度に最終年度を迎えることから、令和8年度から始まる次期「藤枝市耐震改修促進計画」の改訂を現在進められておりますが以下3点について伺います。
①耐震化率について
市が推進している「わが家の地震対策3本柱(住宅の耐震化・家具の転倒防止・非常用品の準備)」のうち、「木造住宅の耐震化」については市民の命を守る重要な施策ですが、旧耐震基準である昭和56年5月以前の木造住宅の藤枝市の耐震化率と、県および近隣市の耐震化率の状況について伺います。
併せて、新耐震基準であっても平成12年(2000年)基準を満たしていない木造住宅の状況について伺います。
②代理受領制度について
住宅の耐震化を進める上では費用面が大きな課題になります。私は「補助金は出ても、一旦業者には全額を支払うので、その点で足踏みをしている。」という声を市民からいただいておりました。
市の担当部署とは何度か意見交換をしてきたところですが、その様な中、次期計画(案)では、新たな取り組みの一つに代理受領制度を位置付けていますので、制度の詳細と実施時期を伺います。
③補助金の増額について
木造住宅の耐震改修には多額の費用が掛かることから、その費用面が理由で耐震改修工事に踏み切れない市民は現実におられます。
補助の上限額を時限的に引き上げて耐震化を推進している自治体もありますが、藤枝市においても補助上限額の拡充を検討できないか伺います。
標題2:奨学金返還への支援について
(1)利用状況と評価について
本市における奨学金の返還支援については、市内の金融機関にご協力をしていただいている「Uターン・地元就職応援プロジェクト」の奨学ローンや奨励金があります。
金融機関との連携協定の調印は令和3年度の途中でしたが事業開始後の利用状況の推移と、地元就職という観点からどのように評価をされているのか伺います。
(2)中小企業向け奨学金返還支援制度について
本年11月3日の静岡新聞6面のコラムで淑徳大学の結城康博教授は、『最近の大学生の約55%は何らかの奨学金を借りており、就職してから奨学金の返済が始まっていくため、学生が就職先を選ぶポイントとして、「賃金」「研修体制」「キャリアビジョン」など以外に、奨学金返済「手当」があるかを確認する学生が増えている。』と述べ、さらに『奨学金の肩代わりは、対外的に若者支援に取り組んでいるといった企業イメージにもつながり、かなり効果的な方策ではないだろうか。』と文章を結ばれています。
さて、本年度の途中から県では「中小企業等奨学金返還支援制度」を始めました。この制度は県・市町・中小企業等が連携をして取り組むことを前提としており、県としても連携する市町を増やしていきたいとの意向がある様です。
そこで、本市としては来年度当初からのタイミングで開始をしていくことは出来ないか、お考えを伺います。