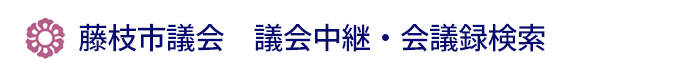質問通告内容
内容
標題1:女性トイレの行列問題について
一人の女性が「トイレの男女別の数」を調べて発信したことが反響を呼び、久しく顧みられることのなかった「女性トイレの行列」に光が当たっている。
女性トイレの行列は女性の誰もが経験し、また連れ添う男性も待たされた経験がある当たり前の光景だが、そこに一石を投じたのが、東京都在住の行政書士百瀬まなみさんだ。百瀬さんの調べによると、公共空間のトイレにおける便器の数は、駅などは女性1に対し男性1.84、空港は1対1.39、公共施設は1対1.50、商業施設は1対1.43、平均で1対1.71だったという。女性の方が便器の数が少ないことに加えて、衣類の上げ下げ、生理用品の交換などで男性よりトイレの利用に時間がかかる。中日本高速道路の調査では、平均利用時間は男性用小便器で35秒、女性の個室では105秒と3倍だった。こうして、女性トイレにばかり渋滞が発生するのである。
「女性ばかりが長蛇の列」という男女のトイレ格差が長年放置されてきた原因は、トイレ設置数に明確な基準がないことである。公共施設や駅、商業施設などのトイレの適正個数を示した公的基準は存在しない。職場にだけは労働安全衛生法に定めがあるが、この法律の「女性用便器は20人ごとに1個以上とし、男性用は小便器が30人ごと1個以上・大便器は60人ごとに1個以上」に従うと、例えば男性65人女性65人の職場では、男性トイレは小便器3つに個室が2つで計5つ、女性は個室が4つと、男性の方がひとつ便器が多くなる。場合によっては法律が職場トイレの格差の原因となっている。
基準がないなか、本市のトイレはどうなっているのか気になるところである。
試しに市役所のトイレの数を聞いたところ、小便器を含めてではあるが、男性用便器が女性用の倍以上あり大変驚かされた。そこで本市の主な公共施設のトイレを回り、困りごとや状況を尋ねてきた。公的な基準がないことで、数だけでなく、便器の形状・暖房便座の有無・広さ・扉の開く方向・多目的トイレの設備などは施設の作られた年代や改修時期により様々であった。男性用サニタリーボックスも生理用ナプキンも所管の課や施設によって設置状況はまちまちであった。子どものおむつは持ち帰りの所もまだまだある。手すりや荷物置がなく、荷物をかけるフックが高すぎて小柄な人は手が届かないなど、ちょっとした工夫で改善できるところもあり、藤枝式快適トイレ計画によるチェック表を作った方が良いのではないかと感じるところであった。
トイレはすべての人に必要な設備であり、施設や地域の印象を決めるところでもある。女性がトイレの行列で困らないように、また本市のトイレ事情の進化を願って以下伺う。
(1) 本市の公共施設におけるトイレの男女格差とその解消を
①男女別のトイレの数は
市役所本庁舎の男女別トイレの数について伺う。併せて、市が管理する主な施設のうち、岡部支所、市立総合病院、藤枝総合運動公園、小中学校(合計)、地区交流センター(合計)、市民会館、蓮華寺池公園、文化センター、生涯学習センターの数も伺う。
②男女のトイレは、面積や数の平等ではなく、待ち時間の平等を
「休憩はトイレ行列で終わる」という女性の声は、以前から出ている。公共施設トイレの公的な基準がない中でも、独自に女性用トイレの行列解消に向けて取り組む自治体がある。山口県萩市は2010年に「公共施設のトイレにかかる整備方針」を策定し、設置割合を男性用小便器1に対して女性用便器を2とする目安を設けた。参考までに、お隣の台湾ではトイレの男女比は1対3、学校や劇場ではなんと1対5に定めているという。
国土交通省でも基準策定に動き出しているが、本市としても、今後の広幡地区交流センターの建替計画などに向けて目安を設けて実施していくべきではないか。
③生涯学習センター女性トイレの改善を
「生涯学習センターの女性トイレで洋式が少なく困る」という声が寄せられた。講座や講演会の休憩や終了後など、みんながいちどきにトイレに向かう際、女性トイレが混雑する。380人の定員のホールを使用するイベントなどでは、休憩時に女性トイレが大混雑となる。1階は南北2か所、2階は1か所の計3ヶ所各トイレがあるが、洋式トイレが各所1つしかないことで、洋式トイレに行列ができてしまう。多目的トイレの洋式2ヶ所を使っても行列だ。和式トイレを使ったことのない子どもや、足腰が弱くなった高齢者は、和式トイレが空いていても使えないのだ。
人数がさほど多くない集まりでも、高齢者が多いと洋式トイレには必ず何人かが並んでしまうそうである。女性トイレの渋滞を避けるため、「会合の途中で抜けてトイレに行く」「イベントの終了前に早めに会場を出て用をすます」など自衛せざるを得ないと、生涯学習センターを利用している女性たちから聞いた。男性トイレにおいてはそういった事態は起きていないという。
多くの行事が行われ市外からの参加者も多い施設であるにもかかわらず、この状態が長く続いている。生涯学習センターの女性トイレの改善を急ぐべきではないか。
(2)緊急事態において女性トイレを十分確保できるように
数々の災害を経て、災害関連死は女性の比率が明らかに高いなど、災害時に女性がより脆弱な立場に置かれることが明らかになっている。トイレは、その大きな原因の一つだ。排泄には個室を必要とする女性にとって、トイレの確保は男性より難しい。トイレに行かないように水分摂取を控えるなどして健康悪化につながる。健康面だけでなくトイレに行く際、性被害を受けるなど犯罪に巻き込まれる事態も相次ぐ。
以前の質問で、国際的な避難所設置基準であるスフィア基準を参考にすると答弁いただいているが、スフィアでは避難所の女性トイレは男性の3倍である。平時から女性トイレが少ないことを鑑みると、事前に女性用として数を確保し、女性トイレは男性の3倍以上必要であることを普段から明示、周知しておく必要があると強く感じられる。
女性専用としてのトイレ資材の確保や、自主防災の運営マニュアルへの明記、市民への広報活動を早急にすべきではないか。
一人の女性が「トイレの男女別の数」を調べて発信したことが反響を呼び、久しく顧みられることのなかった「女性トイレの行列」に光が当たっている。
女性トイレの行列は女性の誰もが経験し、また連れ添う男性も待たされた経験がある当たり前の光景だが、そこに一石を投じたのが、東京都在住の行政書士百瀬まなみさんだ。百瀬さんの調べによると、公共空間のトイレにおける便器の数は、駅などは女性1に対し男性1.84、空港は1対1.39、公共施設は1対1.50、商業施設は1対1.43、平均で1対1.71だったという。女性の方が便器の数が少ないことに加えて、衣類の上げ下げ、生理用品の交換などで男性よりトイレの利用に時間がかかる。中日本高速道路の調査では、平均利用時間は男性用小便器で35秒、女性の個室では105秒と3倍だった。こうして、女性トイレにばかり渋滞が発生するのである。
「女性ばかりが長蛇の列」という男女のトイレ格差が長年放置されてきた原因は、トイレ設置数に明確な基準がないことである。公共施設や駅、商業施設などのトイレの適正個数を示した公的基準は存在しない。職場にだけは労働安全衛生法に定めがあるが、この法律の「女性用便器は20人ごとに1個以上とし、男性用は小便器が30人ごと1個以上・大便器は60人ごとに1個以上」に従うと、例えば男性65人女性65人の職場では、男性トイレは小便器3つに個室が2つで計5つ、女性は個室が4つと、男性の方がひとつ便器が多くなる。場合によっては法律が職場トイレの格差の原因となっている。
基準がないなか、本市のトイレはどうなっているのか気になるところである。
試しに市役所のトイレの数を聞いたところ、小便器を含めてではあるが、男性用便器が女性用の倍以上あり大変驚かされた。そこで本市の主な公共施設のトイレを回り、困りごとや状況を尋ねてきた。公的な基準がないことで、数だけでなく、便器の形状・暖房便座の有無・広さ・扉の開く方向・多目的トイレの設備などは施設の作られた年代や改修時期により様々であった。男性用サニタリーボックスも生理用ナプキンも所管の課や施設によって設置状況はまちまちであった。子どものおむつは持ち帰りの所もまだまだある。手すりや荷物置がなく、荷物をかけるフックが高すぎて小柄な人は手が届かないなど、ちょっとした工夫で改善できるところもあり、藤枝式快適トイレ計画によるチェック表を作った方が良いのではないかと感じるところであった。
トイレはすべての人に必要な設備であり、施設や地域の印象を決めるところでもある。女性がトイレの行列で困らないように、また本市のトイレ事情の進化を願って以下伺う。
(1) 本市の公共施設におけるトイレの男女格差とその解消を
①男女別のトイレの数は
市役所本庁舎の男女別トイレの数について伺う。併せて、市が管理する主な施設のうち、岡部支所、市立総合病院、藤枝総合運動公園、小中学校(合計)、地区交流センター(合計)、市民会館、蓮華寺池公園、文化センター、生涯学習センターの数も伺う。
②男女のトイレは、面積や数の平等ではなく、待ち時間の平等を
「休憩はトイレ行列で終わる」という女性の声は、以前から出ている。公共施設トイレの公的な基準がない中でも、独自に女性用トイレの行列解消に向けて取り組む自治体がある。山口県萩市は2010年に「公共施設のトイレにかかる整備方針」を策定し、設置割合を男性用小便器1に対して女性用便器を2とする目安を設けた。参考までに、お隣の台湾ではトイレの男女比は1対3、学校や劇場ではなんと1対5に定めているという。
国土交通省でも基準策定に動き出しているが、本市としても、今後の広幡地区交流センターの建替計画などに向けて目安を設けて実施していくべきではないか。
③生涯学習センター女性トイレの改善を
「生涯学習センターの女性トイレで洋式が少なく困る」という声が寄せられた。講座や講演会の休憩や終了後など、みんながいちどきにトイレに向かう際、女性トイレが混雑する。380人の定員のホールを使用するイベントなどでは、休憩時に女性トイレが大混雑となる。1階は南北2か所、2階は1か所の計3ヶ所各トイレがあるが、洋式トイレが各所1つしかないことで、洋式トイレに行列ができてしまう。多目的トイレの洋式2ヶ所を使っても行列だ。和式トイレを使ったことのない子どもや、足腰が弱くなった高齢者は、和式トイレが空いていても使えないのだ。
人数がさほど多くない集まりでも、高齢者が多いと洋式トイレには必ず何人かが並んでしまうそうである。女性トイレの渋滞を避けるため、「会合の途中で抜けてトイレに行く」「イベントの終了前に早めに会場を出て用をすます」など自衛せざるを得ないと、生涯学習センターを利用している女性たちから聞いた。男性トイレにおいてはそういった事態は起きていないという。
多くの行事が行われ市外からの参加者も多い施設であるにもかかわらず、この状態が長く続いている。生涯学習センターの女性トイレの改善を急ぐべきではないか。
(2)緊急事態において女性トイレを十分確保できるように
数々の災害を経て、災害関連死は女性の比率が明らかに高いなど、災害時に女性がより脆弱な立場に置かれることが明らかになっている。トイレは、その大きな原因の一つだ。排泄には個室を必要とする女性にとって、トイレの確保は男性より難しい。トイレに行かないように水分摂取を控えるなどして健康悪化につながる。健康面だけでなくトイレに行く際、性被害を受けるなど犯罪に巻き込まれる事態も相次ぐ。
以前の質問で、国際的な避難所設置基準であるスフィア基準を参考にすると答弁いただいているが、スフィアでは避難所の女性トイレは男性の3倍である。平時から女性トイレが少ないことを鑑みると、事前に女性用として数を確保し、女性トイレは男性の3倍以上必要であることを普段から明示、周知しておく必要があると強く感じられる。
女性専用としてのトイレ資材の確保や、自主防災の運営マニュアルへの明記、市民への広報活動を早急にすべきではないか。